
カメラマウントの選び方!メーカー別レンズマウントの種類を徹底解説





写真好きが最初にハマる大きな壁。それが“マウント問題”ではないでしょうか。ボディとレンズをつなぐ小さなリングこそ、カメラの未来を決める要です。この記事では「マウントとは?」という素朴な疑問から、主要メーカーの比較、賢い選び方、そしてレンズ沼との付き合い方まで、肩の力を抜きつつも骨太に掘り下げます。読み終わる頃には、店頭でスペック表をにらむ時間が劇的に減り、代わりにシャッターを切る時間が増えているはず。さあ、あなたの“相棒”を探しに行きましょう。
この記事のサマリー

ボディとレンズをつなぐ「マウント」を理解すれば、機材選びの迷いは半分以下に減る。

Canon・Nikon・Sony・Fujifilm・MFTの長所と弱点を“用途別”に俯瞰できる。

センサーサイズ・AF性能・レンズ資産・将来性。4軸フレームでベストマッチを瞬時に絞り込む。

純正/サードパーティー/アダプター活用のコツを押さえれば、古いレンズも最新ボディで蘇る。

「一本買ったら一本手放す」ルールと防湿庫管理で、レンズ沼と財布を両立させる実践術を提案。
マウントとは?カメラとレンズをつなぐ基礎

カメラのマウントとはボディとレンズの接合規格のことです。ボディとレンズを物理的・電子的に繋ぐ“規格”こそがマウント。マウントが同じならレンズを装着できますが、異なれば物理的に取り付けることはできません。マウントはフランジバックや内径、電子接点など複数の設計要素が絡み合い、互換可否を左右します。ここを押さえるとレンズ選びがロジカルに進み、余計な出費を減らせます。
マウントとは“規格”である
- フランジバック=マウント面〜センサー面の距離
- 内径=マウント開口部の直径
- 電子接点=絞りやAF信号をやり取りする端子
この3つの数値・設計が組み合わさり、「付く/付かない」「画質が出る/ケラれる」を左右します。
バヨネット方式の仕組み
現在主流のバヨネット方式は、レンズ側の爪をボディ側スリットへ差し込み、ひねって固定する構造です。数ミリのズレでも光軸が狂うため、金属部品の加工精度が肝心。着脱が素早く、ホコリが入りにくいのも長所でしょう。
ねじ込み式に比べ回転量が小さいので、動画撮影時のレンズ交換でもタイムロスを最小に抑えられます。野外ロケで雨が降り出しても、素早く望遠へチェンジできる安心感は大きいです。現場でレンズチェンジを多用する報道・スポーツジャンルが後押しし、事実上の世界標準になりました。
ただしメーカー間で爪形状が異なり流用は不可。互換を得るには後述するアダプターの助けが必要になります。
フランジバックと内径の役割
フランジバックはマウント面から撮像面までの距離。ミラーレスはミラーがないぶん短く設計でき、広角レンズが小型化しやすい利点があります。一眼レフ用レンズをミラーレスへ付けやすいのも、この寸法差のおかげです。
一方、内径は大口径レンズの設計自由度を左右します。ニコンZの55 mmはフルサイズ最大級で、F0.95といった超大口径でも周辺減光を抑えやすい設計。対してソニーEは46 mmと細身ながら、サードパーティーの工夫で多彩なレンズが生まれています。
数字の大小には一長一短があり、大きければ重く、高性能なぶんコストも上がりがち。使用目的と予算のバランスを見極めたいところです。
センサーサイズ×マウント:画角とイメージサークルの基礎
「カメラ マウントとは?」を突き詰めるには、センサーサイズとの関係も外せません。フルサイズ・APS-C・マイクロフォーサーズで画角とボケ量が変わり、必要なイメージサークルも変化します。ここを誤ると、ケラレや予期せぬクロップに悩まされます。
焦点距離換算と画角の“体感値”
同じ50mmでも、APS-Cでは約1.5倍、キヤノンAPS-Cでは約1.6倍の画角相当になります。人物中心ならAPS-Cの85mm級は“ちょうど良い寄り”に、フルサイズの35mmは“広めの日常スナップ”に収まりやすい、と覚えるとレンズの選択がスムーズです。
被写界深度も変わるため、同じ絞りでも背景のボケ量はセンサーが大きいほど増えます。ふんわりポートレートなら大きめセンサー+明るい単焦点、旅の軽快さなら小型センサー+小型ズームが快適という判断軸が立ちます。
イメージサークルとケラレ対策
フルサイズ対応レンズはAPS-C機でも使用可で、周辺まですっきり写ります。逆にAPS-C専用レンズをフルサイズに装着すると四隅が暗くなる“ケラレ”が発生します。ソニーEやニコンZのフルサイズ機はAPS-C(DX)レンズ装着時に自動クロップへ切り替え可能で黒縁を回避できます。キヤノンのフルサイズEOS R機にRF-Sレンズを装着した場合も自動で1.6倍クロップに切り替わります。一方でEF-SレンズはフルサイズEFボディには物理的に装着できません。クロップにより記録画素は減少します。
メーカー別のマウント一覧
Canon、Nikon、Sony、Fujifilm、Panasonic/OM SYSTEMなど、主要メーカーごとの現行・代表的マウントを、用途や互換の考え方とあわせて整理します。それぞれのマウント思想とレンズ網をまとめました。得意分野と弱点を把握しておくと、後悔しない選択につながります。
Canonのマウント
キヤノンはEF時代から続く電子制御マウントの老舗。現在はRFマウントへの移行が進み、EFレンズ資産はアダプター経由で活用できます。EF-Mは独立したAPS-Cミラーレス用で、RFとの互換性はありません。今後はRFに統一される見通しです。
マウント名 | 種別 | 対応センサー | フランジバック | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
EF | 一眼レフ | フルサイズ/APS-C | 約44.0mm | 1987年登場の電子制御マウント。豊富なレンズ資産。RF機では純正アダプターで使用可能。 |
EF-S | 一眼レフ | APS-C専用 | 約44.0mm | フルサイズ機には装着不可。EFマウントと同径だが後玉位置が異なる。 |
EF-M | ミラーレス | APS-C専用 | 約18.0mm | EOS Mシリーズ用。RFマウントとは互換なし。EF/EF-Sレンズはアダプター経由で装着可。 |
RF | ミラーレス | フルサイズ/APS-C | 約20.0mm | 現行メイン。大口径・短フランジ設計で高性能。EF/EF-SレンズはアダプターでAF・AE可。 |
ニコンのマウント
ニコンは60年以上の歴史を持つFマウントを維持しつつ、2018年にZマウントを導入。Zは光学設計の自由度が高く、Noct 58mm F0.95のような超大口径レンズも実現しています。FTZアダプターによりFレンズ資産も活かせます。
マウント名 | 種別 | 対応センサー | フランジバック | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
F | 一眼レフ | フルサイズ/APS-C | 約46.5mm | 1959年登場の伝統的マウント。長期互換が特徴。Z機ではFTZアダプターで使用可。 |
Z | ミラーレス | フルサイズ/APS-C | 約16.0mm | 大口径・短フランジ。Z専用レンズで高画質化。Fレンズもアダプターで多く装着可能。 |
Sonyのマウント
ソニーはデジタル一眼レフ時代のAマウントから、現在主流のEマウントへ完全移行済み。Eマウントは仕様が早期に公開され、シグマやタムロンなど多数のメーカーが参入。結果として業界随一のレンズ選択肢を持ちます。
マウント名 | 種別 | 対応センサー | フランジバック | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
A | 一眼レフ/透過ミラー | フルサイズ/APS-C | 約44.5mm | ミノルタ時代のαマウントを継承。LA-EAアダプターでE機にも装着可能。 |
E | ミラーレス | フルサイズ/APS-C | 約18.0mm | 現行マウント。豊富な純正・サードパーティレンズが最大の強み。 |
富士フイルムのマウント
富士フイルムはAPS-C特化のXマウントと、中判用Gマウントの二本立て。Xはコンパクトで描写の良い単焦点が充実し、Gはプロ向けの超高解像システムとして確立しています。
マウント名 | 種別 | 対応センサー | フランジバック | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
X | ミラーレス | APS-C | 約17.7mm | クラシカルなデザインと高画質。XF/XCレンズ群が豊富。 |
G | ミラーレス | 中判(約44×33mm) | 約26.7mm | GFXシリーズ専用。中判サイズの高画質を実現。 |
リコー/ペンタックスのマウント
ペンタックスは堅牢な一眼レフ文化を今も継承。Kマウントは半世紀近い歴史を持ち、旧レンズも活用しやすい設計。中判の645はプロユースで評価が高く、デジタルでも同マウントを継続採用しています。
マウント名 | 種別 | 対応センサー | フランジバック | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
K | 一眼レフ | フルサイズ/APS-C | 約45.46mm | 1975年登場。古いレンズも装着可。寸法互換を長年維持。 |
645 | 一眼レフ/デジタル中判 | 中判(約44×33mm) | 約70.87mm | PENTAX 645シリーズ用。高解像・高階調撮影に対応。 |
パナソニックのマウント
パナソニックはフルサイズLマウントとマイクロフォーサーズを両立。Lはアライアンスにより高級から廉価まで幅広い選択肢があり、MFTは軽量システムとして動画・旅行に根強い人気があります。
マウント名 | 種別 | 対応センサー | フランジバック | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
L | ミラーレス | フルサイズ/APS-C | 約20.0mm | Lマウントアライアンス採用。ライカ・シグマと共通規格。 |
マイクロフォーサーズ(MFT) | ミラーレス | マイクロフォーサーズ | 約19.25mm | 小型軽量でOM SYSTEM製品とも相互装着可能。 |
OM SYSTEMのマウント
オリンパス時代のOMとフォーサーズを経て、現在はパナソニックと共通のマイクロフォーサーズへ移行。小型ボディと強力な手ブレ補正で、軽快な撮影システムを築いています。
マウント名 | 種別 | 対応センサー | フランジバック | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
OM | フィルム一眼レフ | 35mmフィルム | 約46.0mm | フィルム時代のマウント。デジタル機とは直接互換なし。 |
フォーサーズ | デジタル一眼レフ | フォーサーズ | 約38.67mm | 現在はマイクロフォーサーズに移行。アダプターで装着可。 |
ライカのマウント
ライカはレンジファインダー用Mとミラーレス用Lを展開。Mは伝統的な機械精度が魅力で、Lはパナソニック・シグマと共通化し現代的なAF撮影にも対応します。
マウント名 | 種別 | 対応センサー | フランジバック | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
M | レンジファインダー | 35mmフィルム/デジタル | 約27.8mm | 1954年登場。マニュアル専用。高精度の機械構造で評価。 |
L | ミラーレス | フルサイズ/APS-C | 約20.0mm | Lマウントアライアンス共通。各社レンズを相互運用可能。 |
サードパーティ(シグマ・タムロンなど)
シグマとタムロンは主要マウントへ幅広く対応。各メーカーのレンズを純正レンズと呼ぶことに対して、サードパーティと呼ばれています。特にEマウントとLマウントでは純正同等のAF性能を持つレンズも多く、ユーザーの選択肢を大きく広げています。
メーカー | 主な対応マウント | 備考 |
|---|---|---|
シグマ | ソニーE/Lマウント/ニコンZ/富士Xなど | AF対応のContemporary・Artシリーズが主力。 |
タムロン | ソニーE/ニコンZ/富士Xなど | 軽量ズーム・単焦点を多数展開。純正にない焦点域を補完。 |
メーカーが違っても同じマウントを共有する例
有難いことにメーカーが違っても同じマウントを共有する例もあります。
パナソニックとOM SYSTEMは、マイクロフォーサーズ規格を共有しています。どちらのボディでもレンズを相互装着でき、サイズや重量を抑えたシステム構築が可能です。
ライカ・パナソニック・シグマの3社は、Lマウントアライアンスを形成しています。ボディとレンズを自由に組み合わせられる共通規格で、価格帯・画質傾向の幅広さが魅力です。
マイクロフォーサーズやLマウントのように、複数メーカーで共通化された規格も近年増えてきて、利用者にとってシステム選択の幅を広げる要因になっています。
主要メーカーの主力マウント特徴まとめ
メーカー | 主力マウント | 内径 / フランジバック | 得意ワザ | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
Canon | RF | 54 mm / 20 mm | F1.2ズームなど大口径設計 | サードパーティー参入が遅め |
Nikon | Z | 55 mm / 16 mm | 超高解像レンズ多数 | ボディ数がまだ少ない |
Sony | E | 46 mm / 18 mm | レンズ選択肢と動画機豊富 | マウント径が細め |
Fujifilm | X | 44 mm / 17.7 mm | 色再現&小型高画質 | フルサイズ非対応 |
MFT | マイクロフォーサーズ | 40 mm / 19.25 mm | 望遠2倍&軽量 | ボケ量と高感度に限界 |
💡 覚えておきたいキーワード: 「大は小を兼ねる」とは限らない ──内径が大きいほど設計自由度は増えるが、レンズも巨大かつ高価になりやすい。
Canon RFとNikon Z――新世代の大口径派
両者はフランジバック20 mm前後、内径50 mm超の設計で、大口径F1.2単焦点や高性能ズームを得意とします。純正レンズは高価ですが、画質は折り紙つき。既存のEF・F資産をアダプター経由で100 %活かせる点も魅力です。
ただし2024年までサードパーティーAFレンズは少なく、ラインナップ拡充が急務。予算を抑えたいユーザーは中古EF/Fレンズ流用で乗り切るのが現実解でしょう。
Sony Eとマイクロフォーサーズ―小口径でも多芸多才
Sony Eはサードパーティーが豊富で、同じ焦点距離でも価格帯が幅広く、自分のスタイルに合わせたセレクトがしやすい環境です。APS‑Cとフルサイズを一つのマウントでカバーするため、ステップアップ時もボディ買い替えだけで済むメリットがあります。
マイクロフォーサーズ(MFT)は内径約40 mm・フランジバック19 mmと小柄。望遠効果2倍のセンサー特性で、野鳥や航空機撮影を軽量装備で行いたい人に根強い人気。Panasonicの動画機、OM SYSTEMの強力手ブレ補正など個性が際立ちます。
迷わない!4軸のマウント選定フレームワーク
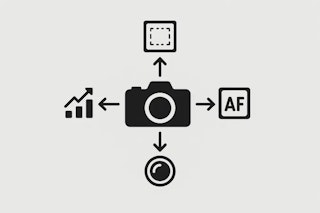
「何を基準に絞るか」で堂々巡りになりがち。センサーサイズ、AF性能、レンズ資産、将来性――四つの軸で考えるフレームワークを紹介します。紙とペンを準備し、チェックリストに○×を付けるだけで選択肢が一気に減るはずです。
- 撮りたい被写体
- 動体→連写・AF速度重視
- 静物→解像・階調重視
- 携行性とサイズ感
- 毎日持つ? 旅限定?
- レンズ資産と予算
- 既存レンズはある? 中古市場は熱い?
- 将来性とアップデート頻度
- ロードマップ公開中? ファーム更新活発?
センサーサイズ×用途マトリクス
被写体が静物中心なら高画素フルサイズ、動体なら連写性能重視のAPS‑Cフラッグシップ、旅行主体ならMFTの軽さが強み。自分の“撮りたい”を列挙し、マトリクスに当てはめると優先度が可視化されます。
予算面ではボディよりレンズが支出の大部分。フルサイズでF2.8ズームを3本揃えると軽く50 万円超。MFTなら同等画角を半額以下で組める例もあります。数字で比較すると決断が早まります。
レンズロードマップと中古市場の二段構え
メーカー公式のレンズロードマップは将来性を占う重要資料。例えばニコンZは2026年までの計画を公表し、超望遠やシネレンズの投入を示唆。Canonは沈黙気味ですが特許情報から動向を探る手もあります。
中古市場の在庫量も要チェック。ソニーEは流通量が多く、状態の良いレンズを安価で確保しやすい一方、MFTは高年式品ほど値崩れしにくい傾向。売却を見越すならリセールバリューも検討材料です。
マウント選びフローチャート
[スタート]
Q.1 あなたは初心者ですか?
【YES】「手軽に始められるAPS-CやMFTがおすすめ」
【NO】「こだわりに合ったフォーマットを選びましょう」
↓
Q.2 「フルサイズへの憧れ」がありますか?
【YES】「フルサイズミラーレスから検討」
【NO】「用途に適したセンサーサイズでOK」
↓
Q.3 主な撮影ジャンルは?
【風景・建築】→「高解像度モデルと広角レンズが充実したニコンZ、ソニーEなど」
【ポートレート】→「フルサイズ+明るい単焦点。キヤノンRFやソニーEが定番」
【スポーツ・野鳥】→「高速AFと超望遠レンズのあるキヤノンRF、ニコンZ、ソニーE」
【スナップ・旅行】→「軽量システムの富士Xやマイクロフォーサーズ。ソニーEの小型機も◎」
【動画メイン】→「パナソニックLマウントやソニーE。キヤノン・ニコンも最近は頑張る」
↓
Q4. レンズ資産はありますか?
【すでに持っている】→「そのマウント継続 or アダプター活用で同メーカー新システム」
【ゼロから揃える】→「将来性・コストを考え人気のソニーEやキヤノンRFも安心」
↓
Q5. サードパーティーレンズ重視?
【重視する】→「ソニーEや富士X、マイクロフォーサーズは選択肢豊富」
【純正で十分】→「どのマウントでもOK。キヤノンRFやニコンZも純正豊富」
↓
Q6. 店頭で触ってしっくり来たのは?
【〇〇社の操作系が好み】→「その直感、正解です! 長く付き合えるマウントに」
【特になし】→「性能・評判で判断しましょう(迷ったら定番のソニーEが無難)」
↓
【ゴール】あなたに最適なマウント(システム)が絞り込めました!
※上記は大まかな流れを示した一例ですが、必ずしも単純にYES/NOで決められるものではありません。ただ、自分の優先事項を整理することで「このマウントなら自分の要求を満たせそうだ」と見えてくるはずです。
マウントアダプター活用術―資産を無駄にしない
古いレンズや他社製レンズを活かす救世主がマウントアダプター。電子接点付き、減速ギア内蔵、スピードブースターなど多種多様。ここでは用途別にベストな選び方と実践上の注意点をまとめました。
- 電子接点付き:純正並みのAF・手ブレ補正を維持。Canon EF→RFが代表例。
- スピードブースター:焦点距離0.7×、F値−1段の魔法。APS‑C動画マンの救世主。
- マニュアル専用:K&F・Fotodioxなど低価格。オールドレンズ遊びに最適。
💡 Tips: ファーム更新は定期チェック。撮影当日アップデート→動作不良は“あるある”なので、必ず前日までにテストを。
電子接点あり/なしの選択基準
AFや絞り制御を使うなら電子接点付きが不可欠。Canon EF→RFの純正アダプターは100 %機能を維持でき安心です。MF主体ならK&FやViltroxの安価な接点なしモデルでも充分。絞り環付きアダプターを使えばオールドレンズの表現力が倍増します。
ただし接点付きはファームウェアの相性問題が起こることも。購入後は必ず最新FWへ更新し、テスト撮影で異常がないか確認しましょう。撮影本番での認識不良は痛いロスにつながります。
スピードブースターで画角を稼ぐ
APS‑CやMFTボディにフルサイズレンズを装着し、0.7×の縮小光学系で画角とF値を稼ぐスピードブースターは、動画ユーザーに人気。Panasonic GH6+Metabones EF→MFTなら、EF24 mmが約17 mm相当になり、F2レンズが約F1.4へ変化します。
メリットは大きいものの、四隅解像やフレア耐性がレンズ本来より低下しやすい点も。逆光シーンでは露出をブラケット撮影しておくと失敗が減ります。
レンズ資産とどう付き合う?沼との向き合い方

“レンズ沼”は楽しい反面、気づけば財布が軽くなる落とし穴。購入判断のルールと保管・メンテナンスを体系化すれば、長い目で見てコストを抑えられます。
- ルール① 一本買ったら一本手放す
- 「焦点距離被り」を防ぎ、資金を回転させる鉄則。
- ルール② 防湿庫は“投資”
- カビ被害=資産価値ゼロ。安価でも良いので導入を。
- ルール③ 物欲リストは寝かせる
- 24時間置くと7割は“見送ってOK”なことに気づく。
「一本買ったら一本手放す」ルール
機材ラックが飽和する前に、同じ焦点距離や用途が重複していないか棚卸ししましょう。フリマアプリでの売却は手数料を加味すると平均7割前後で回収可能。マイナーブランドは専門店委託の方が高く売れるケースもあります。
物欲を抑える具体策として「購入予定リストを一週間寝かせる」方法がおすすめ。一度熱を冷ますことで、本当に必要かどうか客観視できます。
防湿庫とメンテナンスの基本
カビは資産価値を一瞬で奪います。湿度40 %前後をキープする防湿庫が最も安全。導入が難しい場合は乾燥剤+密閉ケースでも代用できますが、交換サイクルを厳守しましょう。
撮影後はブロワーでホコリを除去し、前玉・後玉をマイクロファイバーで軽く拭くだけでも寿命が延びます。防湿庫に戻す前にレンズキャップを外し湿気を飛ばす一手間も大切です。
シーン別ボディとレンズのおすすめコンビネーション
読者の皆さんが具体的にイメージしやすいよう用途別におすすめのカメラボディとレンズの組み合わせをランキング形式で紹介します。「○○を撮りたいけどどの組み合わせが良い?」という疑問にお答えする形で、筆者独断のベスト5を挙げます。いずれも各マウントの特長を活かした鉄板セットです。
シーン | ボディ | レンズ | 理由 |
|---|---|---|---|
旅行 | FE 24–70 mm F2.8 GII | 軽量+暗所に強い | |
ポートレート | RF85 mm F1.2L | 極上ボケと瞳AF | |
スポーツ | Z 100–400 mm | 20 fps連写&超望遠 | |
日常スナップ | 固定23 mm F2 | 軽快・色が美味 | |
動画Vlog | SIGMA 24–70 mm F2.8 DG DN | 無制限録画&手ブレ5軸 |
以上、代表的な組み合わせを挙げました。他にも用途別に最適解はいくつもありますが、この辺りに。大事なのは自分が撮りたい写真に合った機材を選ぶこと、そしてその機材に愛着を持って使いこなすことです。ランキングはあくまで参考程度に、自分だけのベストコンビをぜひ見つけてください。
レンズマウントの歴史と今後の動向
最後に少しマニアックになりますが、レンズマウントの歴史とこれからについて触れておきます。カメラ技術の進化とともにマウント規格も変遷してきました。その背景を知ると、今後の展望も見えてきます。
マウント規格の歴史おさらい
19世紀末に写真が発明されて以来、当初レンズは固定式でしたが、徐々に交換レンズの概念が生まれました。初期はねじ込み式(スクリューマウント)が一般的で、ライカが採用したL39ねじ込み(ライカスクリューマウント)などが著名です。しかしねじ込みは着脱に時間がかかるため、20世紀中頃からバヨネット式マウントが各社で採用されました。
1950~60年代にかけて、各社35mm一眼レフ用マウントが乱立しました。ニコンFマウント(1959)、キヤノンFLマウント(1964)、ペンタックスKマウント(1975)、ミノルタSRマウント(1958)などなど。互換性は皆無で、完全なメーカー間競争です。ただ一方で、当時はサードパーティーでもアダプトールのようにマウント交換式のレンズを作る動きもありました。
1985年、オートフォーカス時代の到来とともに、ミノルタが世界初のAF一眼レフ「α7000」とAマウントを発表。他社も追随し、キヤノンはEFマウント(1987)で大胆に電子制御化・大口径化を図りました。ニコンとペンタックスは従来マウントを維持しつつAF化したため古いレンズとの互換性を比較的保ち、キヤノンは互換を断ち切る代わりに先進的なシステムを構築したという違いがあります。
2000年代に入りデジタル一眼レフ全盛となりますが、マウント自体は各社フィルム時代から継続でした(キヤノンEF、ニコンF、ペンタックスK、ソニーA等)。しかし2008年にパナソニック&オリンパスがミラーレス専用のマイクロフォーサーズマウントを発表し、ここからマウント戦国時代第2幕が始まります。ソニーE(2010)、ニコン1(2011,現終了)、キヤノンEF-M(2012)、富士X(2012)と各社が次々ミラーレス用マウントを投入しました。各社一眼レフとの二本立て戦略が2010年代は続きましたが、2018年にキヤノンRFとニコンZが登場し、一眼レフからミラーレスへの本格移行が決定的になります。
そして2020年代、キヤノン・ニコンは一眼レフ開発を停止し(ペンタックス以外ほぼ全社撤退)、ミラーレスのマウントへ一本化が進みました。ソニーEはミラーレス一本化の成功例としてシェアを伸ばし、キヤノンRF・ニコンZも後発ながら着実にプロユースでの実績を積んでいます。パナソニックは従来のマイクロフォーサーズと並行しつつ、ライカLマウント連合によりフルサイズ市場にも参入しました。富士フイルムはAPS-Cと中判というニッチを独占し、独自の地位を築いています。こうして見ると現在の主要マウントはRF, Z, E, X, L, MFTあたりに収れんされつつあります。各社ともこれらを今後長期的に背負っていく覚悟でしょう。
これからのマウントはどうなる?
では将来的に新たなマウントが登場する可能性はあるのでしょうか?技術革新の節目には新マウント誕生がありますが、当面は今あるミラーレス規格を成熟させるフェーズと見るのが妥当です。各社とも巨額の投資をして新マウントとレンズを揃えたばかりであり、ユーザーも一斉に移行しています。少なくとも今後10年はRF・Z・E等の現行マウントが主力であり続けるでしょう。
むしろ動きがあるとすれば、メーカー間の協業やマウント共有です。すでにマイクロフォーサーズやLマウントが成功例を示しています。最近ではLマウントアライアンスに中国のDJI(ドローン)やASTRODESIGN、日本のブラックマジックデザイン(シネカメラ)なども加わり、多業種に広がっています。将来、例えばキヤノンやニコンがサードパーティーにマウントを開放したり、あるいは新興企業が既存マウントを使ったカメラを作る可能性もゼロではありません。実際2023年には中国からRFマウント採用の格安カメラ(ピクチャーファン社など)も登場し話題になりました。ユーザーとしては選択肢が増えることは歓迎ですね。
また、マウントアダプターのさらなる進化も期待されます。すでに電子接点付きでAF・手ブレ補正が連動するスマートアダプターが一般化し、場合によっては異種マウント間でも純正並みに使えるケースも出てきました。将来は例えば電子接点を介した他社ボディ+レンズの組み合わせが今以上にシームレスになるかもしれません。あるいは光学系内蔵で画角を拡大/縮小するスピードブースター的アダプターの高性能化や、小型化も進む可能性があります。
一方で、カメラの姿そのものが変わる可能性も議論されています。スマートフォンの台頭で一般ユーザー向けカメラは厳しい状況ですが、その分ハイエンド・プロ向けに特化していくでしょう。プロ機では将来的に8Kや16K動画、VR/360°撮影など新分野に対応するかもしれません。その際に既存マウントで光学的に問題が出てくれば、新マウント開発もあり得ます。ただ現行フルサイズマウントはかなり余裕を持って設計されており、例えばニコンZはセンサーシフトでのピクセルシフト合成や星景用の回転センサーなど将来機能も見据えて大径化したと言われます。このように今のマウントでどこまで拡張できるかが各社の腕の見せ所でしょう。
もう一つ、ユーザーコミュニティと中古市場もマウントの寿命に影響します。長く続いたFマウントやEFマウントが今も愛好者に使われているように、仮にメーカーが新規格に移行しても旧マウントがすぐ消えることはありません。オールドレンズブームのように、古いマウントもアダプター経由で第二の人生を送ることができます。実際、フィルムカメラ用の古いレンズがデジタルミラーレスで蘇る現象はここ10年で顕著です。特にミラーレス機はフランジバックが短いのでほとんど全ての一眼レフ用レンズをアダプターで装着できます。マウントアダプターの活用が写真文化に厚みを持たせていると言えるでしょう。
まとめ
長く付き合うシステム選びは、恋人探しに似ています。見た目(デザイン)も大事ですが、性格(操作性)や価値観(レンズ思想)が合わないと長続きしません。本記事で紹介した4軸フレームとアダプター活用術を使い、あなたの撮影スタイルにビタッとハマる相棒を見つけてください。最後にひと言――迷ったらまずシャッターを切りましょう。実写の手応え以上に雄弁な答えは存在しません。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。
あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨
みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!










.jpg?fm=webp&q=75&w=640)