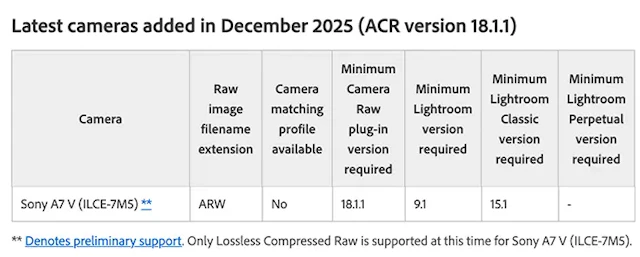.webp?fm=webp&q=75&w=1152)
フルサイズカメラとは?メーカー別のフルサイズカメラ戦略を徹底比較




カメラの「フルサイズ」とは一体何を指すのでしょうか?この記事では、フルサイズ(35mm判)センサーの定義や特徴を紹介し、ニコンやキヤノン、ソニーといった主要メーカーのフルサイズ方針や経緯、他のAPS-C・マイクロフォーサーズとの比較までを徹底解説します!
この記事のサマリー

フルサイズ=36×24mm。APS‑C/MFTと面積・画角・ボケ・高感度の違いを整理

2024–2025の要点:Z6IIIの「部分積層」、Z5 II投入、EOS R1/R5 II、α9 IIIのGS、S9とSL3/SL3‑S

メーカー毎のフルサイズ方針比較:中核×裾野(ニコン)、旗艦再設計(キヤノン)、技術×開放(ソニー)、連合の厚み(L)
フルサイズセンサー(35mm判)とは何か:最短で分かる基礎
.webp?w=320)
フルサイズとは、デジタルカメラのイメージセンサーサイズの一種で、かつての35mmフィルム(135フィルム)とほぼ同じ大きさの撮像素子を指します。具体的には約36×24mmの画面サイズで、フィルムカメラ時代に広く使われたライカ判(24×36mm)フォーマットに相当します。
英語では「35mm full-frame(フルフレーム)」とも呼ばれ、日本語では単に「フルサイズ」と略されることが多いです。「フル(=完全)」という言葉には、「従来の標準フィルムサイズをそのまま満たす」という意味合いが込められています。
イメージセンサーサイズとは
.webp?w=320)
まずイメージセンサーサイズとは、カメラ内部で光を受け取る撮像素子の大きさのことです。代表的な規格には、35mmフルサイズ(36×24mm)、APS‑C(約23.5×15.6mm)、マイクロフォーサーズ(17.3×13.0mm)、1インチ(13.2×8.8mm)などがあります。
一般的にセンサーが大きいほど同じ条件でノイズに強く、階調に余裕が生まれ、同構図でのボケ量も増えます。一方で小さいセンサーは機材の小型軽量化とコスト面で有利で、望遠が届きやすい(=画角が狭くなる)という使い勝手の利点があります。
実はフルサイズは最大サイズではない
「フルサイズ」とはいえ、このセンサーがカメラで最大サイズというわけではありません。35mm判より大きい中判デジタル(ブローニーフィルム相当)などの撮像素子も存在し、フルサイズはあくまで一般的な35mm判基準での“フル”という位置づけです。それでも、スマートフォンやコンパクトカメラの極小センサーと比べれば桁違いに大きく、本格的な一眼カメラに搭載される大型センサーとして広く認識されています。
フルサイズ vs 他のセンサーサイズ:何がどう違う?

カメラのセンサーサイズには、フルサイズ以外にもAPS-Cやマイクロフォーサーズ(MFT)など複数の規格があります。それぞれサイズが異なることで、写真の写りやカメラの特性にも違いが生まれます。ここでは主なセンサーサイズごとの違いを比較し、どのようなシーン・ユーザーに適しているかを見てみましょう。
センサーサイズの一覧と基本スペック
まず代表的なセンサーサイズの大きさを整理します(対角長はおおよその値)。
センサーサイズ | 大きさ | 概要 |
|---|---|---|
35mmフルサイズ | 約36×24mm(対角43mm) | 基準となるサイズ規格で、一眼レフ・ミラーレスの上位機に採用 |
APS-Cサイズ | 約23.6×15.8mm(対角28mm前後) | フルサイズの面積約40%程度で、一眼の普及帯・中級機に最も広く使われる。 |
マイクロフォーサーズ | 約17.3×13.0mm(対角21.6mm) | フルサイズ面積の約25%で、オリンパス・パナソニックのミラーレスに採用。4/3型とも呼ばれる。 |
1インチ型 | 約13.2×8.8mm(対角15.9mm) | 高級コンデジや一部小型機に使用。フルサイズ面積比で約8~9%。 |
スマートフォン(1/2.3型相当) | 約6.2×4.6mm(対角7.7mm) | 機種により異なるが、一般スマホはこの程度。フルサイズ比わずか数%。 |
上記のように、センサーサイズはフルサイズ → APS-C → マイクロフォーサーズ → 1インチ → コンデジ/スマホの順に小さくなっていきます。それでは、このサイズ差が具体的に撮影結果やカメラ性能にどう影響するか、主要なポイントごとに比較してみましょう。
写る範囲(画角)の違い
センサーサイズが変わると画角(写る範囲)が変化します。フルサイズを基準とすると、APS-Cは約1.5倍、マイクロフォーサーズは約2倍の「望遠効果(クロップ)」が生じます。
たとえば50mmレンズで同じ位置から撮影した場合はこのような違いがでます。
センサーサイズ | 50mmレンズで撮影した場合 |
|---|---|
フルサイズ | レンズ表記通りの画角(標準レンズらしい自然な範囲)が写る。 |
APS-C | センサーが小さいぶん中央だけを切り取る形になり、フルサイズの約1.5倍ズームアップした狭い範囲が写る。50mmレンズが実質75mm相当の画角になるイメージです。 |
マイクロフォーサーズ(MFT) | フルサイズ比約2倍のクロップ。50mmが100mm相当になり、かなり望遠的な画角になります。 |
この性質から、広角を活かすならフルサイズ有利、望遠を稼ぐなら小さいセンサー有利という傾向があります。野鳥や航空機撮影など遠距離の被写体にはAPS-C/MFTが「望遠1.5~2倍ブースト」のメリットを発揮し、逆に風景や建築など広角重視ではフルサイズが強みを見せます。実際、プロの中にも「超望遠域では軽量なAPS-C機をあえて使う」という人もおり、状況次第で使い分けられています。
背景ボケ(被写界深度)の違い
センサーサイズが大きいほど背景ボケは大きくなります。前述した通り、フルサイズは浅い被写界深度で背景をぼかしやすいのが特長です。対してAPS-Cやマイクロフォーサーズでは同じ構図・F値でもピントの合う範囲が広く、背景のボケ量は控えめになります。この差はポートレートやマクロ撮影などで顕著です。ボケ味重視ならフルサイズが有利ですが、逆に風景全体にピントを合わせたい場合などは小さいセンサーの深い被写界深度が有利になるケースもあります。
いずれにせよ、ボケの大きさはフルサイズ > APS-C > MFT(マイクロフォーサーズ)の順で大きくなると覚えておきましょう
高感度耐性・画質の違い
暗所性能やダイナミックレンジはセンサーが大きいほど有利です。フルサイズは各画素が大きく光を多く集められるため、同じISO感度でもノイズが少なくクリアな画像が得られます。APS-CやMFTは高感度でややノイズが増えますが、最近のモデルは画像処理技術の進歩でかなり健闘しており十分に高い表現力を持っています。
ただ、極限の暗所(天の川の撮影など)ではフルサイズのほうが余裕があるのは確かです。またダイナミックレンジ(明暗差の再現幅)もフルサイズ機のほうが僅かな階調の違いを滑らかに表現できる傾向があります。一方、小さいセンサー機でも近年はノイズ低減技術やHDR機能が発達し、例えば最新APS-C機で撮った夜景でも豊かな階調が再現できるケースも多々報告されています。総じて言えば、画質面ではフルサイズ有利だが最新の小型センサー機も想像以上に健闘しているというのが実情です。
機材の大きさ・システム全体の違い
カメラ・レンズのサイズと重量はセンサーサイズに直結します。フルサイズ対応のボディやレンズは総じて大きく重くなりがちで、APS-CやMFTはコンパクトで軽量な製品が多いです。特にマイクロフォーサーズはシステム全体が小さくできるため、レンズ交換式でありながら女性や初心者でも扱いやすいサイズ感を実現しています。
対するフルサイズ機は本格的な撮影に耐える耐久性や操作系を備えている半面、どうしても荷物が大きくます。ただし前述のように近年はフルサイズ機でも小型モデルが登場しており、「フルサイズ=大きく重い」という図式は崩れつつあります。
ソニーα7シリーズやキヤノンEOS RPなど、小型軽量を売りにしたフルサイズ機も選択肢に増えてきました。サイズ・重量はセンサーサイズとトレードオフの関係ではあるが、技術進歩で差は縮まりつつあると言えるでしょう。
フルサイズに2024–2025で起こった主要トピック
ここ1〜2年はテクノロジーと製品戦略の両面で大きく動きました。
まずミドル帯の常識を塗り替えたのがNikon Z6III。世界初の“部分積層CMOS”でZ6II比約3.5倍の読み出し、プリキャプチャ最大120fps、内部6K N‑RAW/ProRes RAWに対応し、電子シャッター運用と動画領域を一段引き上げました。
ニコンがフルサイズ強化。Z6IIIの台頭とZ5 IIの受け皿
.webp?w=320)
Z6IIIは部分積層CMOS×EXPEED 7でAF・動画・電子シャッターの実用域を拡大。読み出し高速化でローリング耐性も改善しました。
2025年4月発売のZ5 IIは“初めてのフルサイズ”として導入ハードルを下げた価格に対応。BCN+R公開データにて発売直後の国内「フルサイズミラーレス」月間でニコンが初の1位を獲得する原動力となりました。
キヤノン&ソニーがトップエンドを再定義
.webp?w=320)
キヤノンは2024年7月17日にEOS R1/EOS R5 Mark IIを同時発表。新処理系と深層学習AFでプロ現場を再設計しました。
ソニーはα9 IIIでフルサイズ初のグローバルシャッターを実装。120fps・ブラックアウトフリーでスポーツ/報道領域のワークフローを刷新しました。
Lマウントの厚み:S9/SL3/SL3‑S+加盟拡大
.webp?w=320)
パナソニックは小型志向のLUMIX S9を投入。ライカは高品位のSL3(2024年3月)、速度・動画を重視したSL3‑S(2025年1月)で棲み分けを明確化。
加えて2025年9月1日、ViltroxがL‑Mount Allianceに正式加盟。手頃な価格帯の選択肢が広がりました。
メーカー別のフルサイズ戦略
同じフルサイズでも「強みの出し方」は各社で異なります。購買判断に必要な点に絞って、ボディ/レンズ生態系、価格/重量バランスまでまとめします。
ニコン(Nikon):中核強化×裾野拡大
Z6IIIの部分積層CMOS×EXPEED 7でAF・動画・電子シャッターの実用域が拡張。ミドル帯の“基準機”に躍進しました。
エントリーはZ5 IIで受け皿を広げ、国内2025年4月のフルサイズミラーレス月間1位を獲得。TamronのZマウント対応(28‑75mm F2.8 G2や150‑500mm など)も追い風です。
動画面では2024年のRED買収によりシネ領域の知見が接続。2025年2月にはREDがV‑RAPTOR [X] Z Mount/KOMODO‑X Z Mountを発表し、Zマウントの広がりが具体化しました。
キヤノン(Canon):旗艦を再設計しRF価値を守る
EOS R1/R5 Mark IIでトップエンドを再定義。新処理プラットフォームと深層学習AFで、報道・スポーツ現場の即応性を底上げしました。
RFマウントはAFサードをAPS‑Cから公式開放。SIGMA(DC DN系)とTAMRON 11‑20mm F2.8(RF‑S)が加わり、エコシステムの裾野が広がりました。
ソニー(Sony):技術ドライブ×開放エコシステム
α9 IIIのグローバルシャッターで“歪み”と“フリッカー”課題を原理的に回避。120fps連写とブラックアウトフリーで決定的瞬間を電子シャッターで狙えます。
Eマウントは長年の開放戦略でサードが最厚。ボディ/レンズの選択肢が広く、動画〜静止画の総合力で“ハブ”の地位を維持しています。
Lマウント連合(Leica/Panasonic/SIGMA ほか):幅の広さ
小型のLUMIX S9で“配信時代”の軽快さ、Leica SL3/SL3‑Sでプレミアムと速度・動画を棲み分け。同じマウント内で広い選択ができるのが強みです。
2025年9月にViltroxが正式加盟し、価格帯の裾野がさらに拡大。連合の強みが一段と際立ってきました。
ペンタックス(RICOH):一眼レフ×フルサイズと“フィルム回帰”
K‑1 Mark IIでフルサイズ一眼レフを継続。OVF派の最後の砦としてのポジションを確立しています。
2024年にはハーフ判のフィルムコンパクト「PENTAX 17」を発売。フィルムの楽しさを前面に出し、ブランドの個性が際立っています。
富士フイルム(Fujifilm):フルサイズやらない宣言でAPS‑C+中判に集中
「フルサイズはやらない」と明言してきた経緯があり、X(APS‑C)とGFX(中判)で差別化を継続。フルサイズを“挟み撃ち”する戦略です。
2025年も二極集中を再確認する発言が継続。自社の強みを磨く姿勢が明確で、選択肢としての存在感はむしろ増しています。
用途別でのフルサイズの選び方
ここでは用途別で比較し、初めての一台/次の一台を絞り込むための軸を示します。
今選ぶ万能ミドルはNikon Z6III。部分積層CMOS×EXPEED 7で読み出し高速化、内部6K N‑RAW/ProRes RAWで動画も妥協なし。ミドル帯の“基準”に相応しい一台です。
初めてのフルサイズ
失敗率の低さで選ぶならNikon Z5 II。AFやEVF、操作が底上げされ、写真も動画も「最初の壁」を低くしてくれます。
レンズはZ 28‑75mm F2.8(Tamron A063Z)や150‑500mmなど“軽・安・速”の選択肢が実用的。純正+サードで組みやすいのが魅力です。
フラッグシップ/ハイエンド
静止画主体のフラッグシップならEOS R1。新プラットフォームと深層学習AFで報道・スポーツの現場を想定。万能の柱はEOS R5 Mark IIです。
最速特化はソニーα9 III。グローバルシャッター×120fps×ブラックアウトフリーの連写で、電子シャッター運用を“主戦”にできます。
軽快クリエイター/プレミアム志向
軽さと“撮って出し”の気持ちよさで選ぶならLUMIX S9。リアルタイムLUTで作品化が速い。
高品位志向はLeica SL3、速度・動画の両取りはSL3‑S。Lマウント内で明快に棲み分けされ、投資の方向性が立てやすいです。
2025年時点:メーカー各社のフルサイズ戦略比較表のサマリ
メーカー | 戦略テーマ | 主な動向・特徴 |
|---|---|---|
ニコン | 中核強化+裾野拡大 | Z6IIIでミドルレンジを底上げし、Z5 IIでエントリー層を拡大。さらにRED買収とRED製Zマウント機の発表により、動画領域でも存在感を強化。 |
キヤノン | 旗艦再定義 | R1とR5 IIでプロフェッショナル領域を盤石化。RFマウントはAPS-C対応とサードパーティ開放で裾野を広げつつ、ブランド価値を維持。 |
ソニー | 技術×開放 | α9 IIIのグローバルシャッターで高速撮影を牽引。Eマウントはサードパーティの参入が最も厚く、開かれたエコシステムを確立。 |
Lマウント | 連合の厚み | S9・SL3・SL3-Sに加え、2025年9月にViltroxが加盟。高級から手頃な価格帯まで幅広いレンジをカバーし、Lマウント連合の裾野を拡大。 |
ペンタックス | 唯一無二のOVF | K-1 Mark IIでフルサイズ一眼レフの継続を明確化。さらにPENTAX 17の投入でフィルム回帰の流れを後押し。 |
まとめ
「カメラ フルサイズとは?」の端的な答えは36×24mm。画角・ボケ・暗所の物理的優位が他センサーサイズと比較した魅力です。2024–2025年はフルサイズカメラの動きが大きく、Z6IIIの“部分積層”とZ5 IIの受け皿、EOS R1/R5 IIの旗艦再設計、α9 IIIのGS、Lマウントの厚みで輪郭が一層クリアになりました。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント(X /Threads /Instagram /TikTok /YouTube )で毎日発信中。
あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨
みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!







.jpg?fm=webp&q=75&w=640)