
Nikon Z5II vs Z6III徹底比較、性能差と選び方完全ガイド【2026年版】




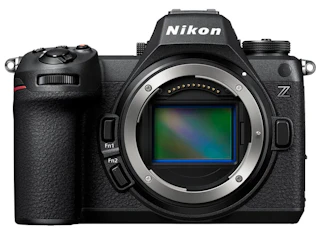
Z5IIとZ6III、結局どっちが自分に合うのか?にズバッと答えます。この記事では撮影シーンや予算配分を前提に、両機の“本当に差が出る”ポイントだけを整理。発売状況と基本スペックの要点から、センサー特性、AF追従、連写・プリキャプチャ、動画機能、EVF・操作性、手ブレ補正、ワークフロー(カード/電源/接続)、価格の落としどころまで、事実ベースで分かりやすく掘り下げました。
この記事のサマリー

Z6IIIは部分積層センサー+CFexpress対応、動画・連写が大幅優位

Z5IIはデュアルSD+EXPEED 7で静止画主体の高コスパを実現

両機とも-10EVのAF検出やプリキャプチャなど先進機能を共有

EVFはZ6IIIが576万ドット/最大4000nit、Z5IIは369万ドット/最大3000nit

用途で選ぶ:動画・動体=Z6III/旅行・ポートレート中心=Z5II
基本情報のおさらい:発売状況と主要スペック

Z6IIIは2024年に発表された24.5MPフルサイズ機、一方のZ5IIは2025年登場の24.5MPフルサイズ機。価格レンジはZ5IIが下位、Z6IIIが上位帯です。
Z6IIIは世界初の部分積層CMOSと6K/60p内部RAW、FHD/240pまでのスローモーションが目玉で、EVFは4000nit/DCI‑P3で「最も明るい」と謳われています。一方Z5IIは一段階手頃な価格で登場し、EXPEED 7採用・N‑RAWをSDカードへ内部記録できる初のフルサイズZです。
発売時期・価格レンジ
Z6IIIはボディ396,000円(税込)、Z5IIは258,500円(税込)で、価格差は約14万円です。Z6IIIは24年7月発売、Z5IIはおよそ9ヶ月後の25年4月発売です。
1年以内に発売されているこの2機材は特に比較される機会が多く、海外メディアDigital Camera Worldも「動画・将来性を重視するならZ6III、静止画中心やVlog程度ならZ5II」と整理しています。価格差を画質だけでなく、動画/連写/操作系の広がりとして捉えるのが合理的です。
Z5II・Z6III主要スペック比較
項目 | Z5II | Z6III |
|---|---|---|
センサー | 24.5MP BSI | 24.5MP 部分積層 |
動画 | 4K/60p※DXクロップ, 4K/30p FF, FHD/120p, N‑RAW内部 | 6K/60p N‑RAW, 5.4K ProRes 422 HQ, 4K/120p, FHD/240p |
連写 | RAW 最大約10fps(サイレントON時)/JPEG 拡張約14–15fps・HSF+ 15/30fps | RAW 最大約20fps(電子)/JPEG HSF+ 60/120fps |
EVF | 369万ドット/最大3000nit | 576万ドット/最大4000nit |
カード | SD(UHS‑II)×2 | CFexpress Type‑B + SD(UHS‑II) |
AF検出範囲 | ‑10〜+19EV | ‑10〜+19EV |
質量(バッテリー込) | 約700g | 約760g |
2機種の違いは「センサー構造」「連写速度」「動画性能」「EVFの表示品質」「記録メディア仕様」に集約されます。
【決定版】Z5II vs Z6III 比較早見表
まずは忙しい人はここだけ見ればokな比較サマリです。以降は各観点でのZ6IIIとZ5IIの詳細な比較をみていきます。
観点 | Z5II | Z6III | 選び方のポイント |
|---|---|---|---|
センサー構造 | BSI CMOS(裏面照射型) | 部分積層CMOS(高速読み出し) | 静止画中心ならZ5IIの安定感、高速連写や動画ならZ6IIIのスピードを。 |
画像処理エンジン | EXPEED 7(最新世代) | EXPEED 7 | どちらも最新世代で画質傾向は近い。Z6IIIは処理速度がさらに上。 |
AF性能 | −10EV対応、AF-A搭載、追従性能は十分 | −10EV対応、フラッグシップ譲りの被写体検出 | 動体撮影はZ6IIIが圧倒。静物中心ならZ5IIで問題なし。 |
連写性能/プリキャプチャ | RAW約10fps、JPEG最大30fps、プリキャプチャJPEG限定 | RAW約20fps、JPEG60/120fps、プリキャプチャJPEG限定 | 動き物を狙うならZ6III、一般撮影はZ5IIで十分。 |
動画性能 | 4K/30pフルフレーム、4K/60p DXクロップ、N-RAW内部記録対応 | N-RAW 6K/60p、ProRes RAW、4K/120p、FHD/240p対応 | 動画重視はZ6III一択。Z5IIは日常動画やVlogに好適。 |
EVF・モニター | 369万ドット/3000nit/バリアングル液晶 | 576万ドット/4000nit/バリアングル液晶 | EVFの精細さと明るさでZ6IIIが上。Z5IIでも十分実用レベル。 |
手ブレ補正(IBIS) | 最大7.5段(フォーカスポイントVR対応) | 最大8段(中心部基準) | 手ブレ補正はほぼ互角。構図端の安定性はZ5IIが優れる。 |
記録メディア | SD UHS-II×2(デュアルスロット) | CFexpress Type-B+SD(UHS-II) | コスト重視ならZ5II、高速書き込みならZ6III。 |
操作性/ボディ設計 | モードダイヤル式、シンプル操作、防塵防滴 | 上面液晶付き、Z8譲りの操作系、防塵防滴強化 | 初心者はZ5IIが扱いやすく、上級者はZ6IIIの操作性が快適。 |
価格帯(2026年時点) | 258,500円(税込) | 396,000円(税込) | 価格差約14万円。性能をフルに使う撮影スタイルかで判断。 |
総合評価 | 静止画・旅・コスパ重視の万能型 | 動体・動画・プロ志向のハイブリッド機 | 出番の8割が静止画中心ならZ5II、動画や動体重視ならZ6III。 |
撮影シーンで分けるなら、動体・動画中心ならZ6III、風景・人物・日常中心ならZ5IIが最適解です。
- Z6III は「スピード×動画×EVF品質」で上位機譲りの完成度。部分積層センサーにより電子シャッター時の歪みが少なく、スポーツ・報道・映像制作に最適
- Z5II は「安定×低価格×静止画性能」に振ったバランス機。AF-AやN-RAW内部記録など上位技術を採用しつつ、デュアルSD運用でコストを抑えたいユーザーに向く
Z5IIとZ6IIIの「画作り」の比較:センサー構造と実写耐性

Z6IIIは「部分積層(Partially‑stacked)」CMOSで読み出しを高速化し、動体・動画で効く下地を獲得。一方Z5IIはBSI化+EXPEED 7により、高感度域の粘りと処理余裕をコンパクトにまとめています。どちらも24.5MPで階調・ノイズのバランスが良く、レンズ解像の受け皿として扱いやすいのが共通点です。
部分積層の狙い:スピードを画質劣化なく引き出す
Z6IIIの肝は「読み出し高速化=ローリング歪み低減=電子シャッター実用域の拡張」。高速連写や4K120pなど、動体直結のスペックが伸び、機会損失を減らせます。
Peta Pixelは実機レビューで「Z6IIIをメカと電子でDR差がほぼ無いが低ISOではZ6IIより約1段低い」と整理しつつ、「この価格帯で最有力のフルサイズ・ハイブリッド機」と総括しています。さらに電子シャッター時でもダイナミックレンジ低下が実質見分けにくいと報告しています。
一方で風景の階調追い込みでは露出設計に注意が必要な場面もありますが、総じて「高速化メリットが勝りやすい」設計です。動体・動画・ハイブリッド運用ではZ6IIIの優位が明確です。
BSI+EXPEED 7の安定感:暗所と扱いやすさ
一方でZ5IIはEXPEED 7によるAF・高感度の底上げが効きます。SheClicksはZ5IIを「このレベルで最も多用途」と評し、低照度AF(‑10EV)と価格バランスを強調。Thom Hoganも読み出し50.8msへの改善を挙げ、「Z5→Z5IIの実用強化」と結論づけています。ピクセルシフト(ソフト合成)対応で、解像優先のワークにも拡張性があります。
AF・被写体検出の比較:-10EV、3Dトラッキング、AF‑Aの使いどころ
両機とも-10EVまで食い下がる検出範囲と3Dトラッキング、9種の被写体検出に対応。暗い体育館や夕景ポートレートでも合焦率が安定します。Z5IIはフルサイズZで初のAF‑A(AF‑S/AF‑C自動切替)を搭載し、動静混在シーンでの迷いを軽減します。
動体追従の安定感:部活・運動会・都市スナップ
Z6IIIは読み出し高速化の恩恵で、AF追従下でも高フレームを維持。20fps RAWや60/120fps JPEGのハイフレームとプリキャプチャの組み合わせで“押した瞬間の前”まで回収できます。
Birdsモードの行方:最新ファームの確認
Z6IIIにはファーム2.00で専用の「Birds」モードが追加。鳥の顔・瞳を優先して追尾しやすくなりました。Z5IIも同系統の被写体検出を備え、AF‑Aの存在は歩留まりの底上げに直結します。
連写・プリキャプチャの比較:記録の厚みをどう作るか
Z6IIIとZ5IIの比較でもっとも差が出やすいのがシャッター周り。Z6IIIはRAW最大約20fps(電子)、JPEG 60/120fps(HSF+)。Z5IIはRAW最大約10fps(サイレントON時)、JPEGは拡張で約14/15fps、HSF+で15/30fps。両機ともプリリリースキャプチャ対応で瞬間回収力を高められます。
モード | Z6III | Z5II | 特徴・使い分けの目安 |
|---|---|---|---|
RAW連写(電子シャッター) | 最大約20コマ/秒 | 最大約10コマ/秒(サイレントON時) | 動体やスポーツではZ6IIIが圧倒的に余裕。Z5IIは日常・静止被写体向き。 |
JPEG連写(拡張モード) | 60コマ/秒(C60)/120コマ/秒(C120) | 約14・15コマ/秒(拡張) | Z6IIIは一瞬の動きを確実に捉えたいプロ・動体撮影向け。Z5IIは軽いスポーツや子ども撮影で十分。 |
HSF+(High-Speed Frame+) | C60/C120(JPEG限定) | C15/C30(JPEG限定) | どちらもプリキャプチャー機能と併用可能。Z6IIIはより広い被写体対応、Z5IIは軽量データ運用向き。 |
プリキャプチャー | JPEG限定・最大1秒前まで記録 | JPEG限定・最大1秒前まで記録 | 押し遅れ対策として共通。RAW非対応の点は同じ。 |
メカシャッター連写(RAW) | 約14コマ/秒(メカ/12bit) | 約7.8コマ/秒(メカ/12bit) | 機械シャッター撮影でもZ6IIIは倍近い速度で動体対応力が高い。 |
スポーツ・野鳥・モータースポーツ
Z6IIIは「速度」と「AF追従」が同時成立。打球や接触の瞬間、視線変化も拾いやすく、バッファ・書込速度の恩恵を活かすにはCFexpressが実質必須です。
スナップ・ブライダル・舞台
静粛性が求められる現場では電子シャッターが有効。Z6IIIはローリング歪みが抑えやすく、無音運用の歩留まりが良好。静物中心ならZ5IIでも十分ですが、急な動きにはプリキャプチャの有無が差になります。
動画機能の比較:素材の歩留まりと編集耐性で選ぶ
Z6IIIはN‑RAW 6K/60p、ProRes RAW、5.4K ProRes 422 HQ、4K/120p、FHD/240pまで内蔵。Z5IIは4K/60p(DXクロップ)・4K/30pフルフレーム、FHD/120p、そしてN‑RAWをSDカードに内部記録できます。編集耐性・スローモーション・記録ビットレートの余裕はZ6IIIが優位、身軽さとメディア費はZ5IIが有利です。
撮影モード | Z6III | Z5II | 実用面でのポイント |
|---|---|---|---|
最高解像度 | N-RAW 6K/60p(内部記録) | 4K/60p(DXクロップ) | Z6IIIは6K収録で編集耐性が高く、リフレームも自由。Z5IIはクロップながら軽装収録に対応。 |
高品質コーデック | ProRes RAW(6K/30p)、5.4K ProRes 422 HQ | N-RAW 12bitをSDカードに内部記録可能 | Z6IIIはプロ制作向けの内部RAW、Z5IIはコストを抑えたRAW収録が魅力。 |
4K撮影 | 4K/120p(全幅・ハイスピード対応) | 4K/30pフルフレーム/4K/60p DXクロップ | Z6IIIは高速度撮影対応でスロー表現が可能。Z5IIは日常用途に十分。 |
フルHD撮影 | 最大240p | 最大120p | Z6IIIはより滑らかなスーパースロー映像に対応。 |
10bitログ撮影 | N-Log/HLG対応 | N-Log/HLG対応 | 両機ともカラーグレーディング前提の10bit収録に対応。 |
記録メディア | CFexpress Type-B+SD(UHS-II) | SD(UHS-II)×2 | Z6IIIは高速書き込みで大容量RAW動画に対応。Z5IIは手軽に運用可能。 |
6K RAWと4K120pの現場効果(Z6III)
オーバーサンプリング4K/60pや4K/120p、波形表示など支援が充実。動画主体ならCFexpress前提でストレスの少ない運用が定石です。PetaPixelやDCWはZ6IIIのハイブリッド性能を高く評価しています。
N‑RAWをSDに内部記録(Z5II)
「SDでN‑RAW」というコスト面のメリットはZ5IIの個性。Vlogや小規模取材など、メディア費を抑えつつ10bitやN‑Log運用もこなせます。4K/60pはDXクロップですが、4K/30pはフルフレーム読み出しです。
EVF・背面モニター・操作性の比較:見え方は仕上がりに直結

ファインダーの見えはピント・露出判断に直結。Z6IIIは576万ドット/最大4000cd/m²で“クラス最明るい”EVF、色域もDCI‑P3対応。Z5IIは369万ドット/最大3000cd/m²で十分明るい視認性です。どちらも3.2型・約210万ドットのバリアングル式を備えます。
表示品位の差が歩留まりに効く
強い外光下でもZ6IIIの高輝度EVFはピーキングやハイライト判断が速い。マニュアルフォーカスの微調整もラクで、表示支援と合わせて露出決断が迅速です。
物理操作とImaging Cloud
両機ともニコンImaging Cloudと連携し、レシピ適用や転送の自動化をサポート。Z5IIの「Picture Control」ボタンは色決めの呼び出しを簡略化し、JPEG納品の手戻りを抑えられます。
手ブレ補正と低照度の比較:現場の“歩留まり装置”を比較
両機ともボディ内5軸手ブレ補正を搭載。Z5IIはフォーカスポイントVRにより、フレーム周辺でも補正が効きやすい設計で、中央最大7.5段・周辺6段(CIPA基準)が公表されています。暗所AFの-10EV対応と合わせ、夜景・屋内撮影の成功率は高いです。
静止画:遅めのシャッターでも破綻しにくい
Z6IIIは高感度時のAF追従と補正の安定感が人物・スナップの歩留まりを底上げ。Z5IIは旅行や日常記録の軽装セットで強く、F1.8単焦点と組むと手持ち夜景の成功率が上がります。
動画:歩き撮り・パン時の画の安定
Z6IIIは高フレーム動画でも補正の粘りが良好で、ワンオペ撮影に好適。Z5IIもFHD/120pで被写体の動きを滑らかに演出でき、Vlogやレビュー撮影で扱いやすいです。いずれもレンズ側VRと協調します。
カードスロット・電源・入出力の比較:ワークフローの現実解
運用の要は「どの媒体に何を記録するか」。Z6IIIはCFexpress Type‑B+SDのデュアルで、RAW高速連写や高ビットレート動画の本番運用に最適。Z5IIはUHS‑II SD×2で、バックアップ運用の容易さ・低コストが強みです。電源はいずれもEN‑EL15c世代でUSB‑PD給電/充電に対応します。
高速 vs 低コスト:現場の優先順位で選ぶ
6K RAWや4K120p、高速連写を多用するならZ6III+CFexpressは実質必須。書き込み待ちを減らし、取り逃しリスクを低減できます。対してZ5IIはN‑RAWをSDに内部記録でき、メディア費を抑えつつバックアップも組みやすい構成です。
入出力・表示支援
ヘッドホン/マイク、HDMI、USB‑C等の基本I/Oは共通。Z6IIIは波形表示など撮影支援が充実し、露出の“当て勘”を減らせます。Z5IIも必要十分の表示と操作で、Vlogやレビュー撮影に適しています。
価格とコスパ:レンズを含めた総額で考える
Z6III・Z5IIの比較で最後に悩むのが予算配分。Digital Camera Worldは実機レビューの上で「動画重視ならZ6III/静止画中心ならZ5IIでレンズに予算を回す」を推奨。ボディ価格差14万円で上質な単焦点1本、または高性能標準ズームに届くのは現実的な魅力です。
投資対効果の分岐点
6K RAW/4K120p、20fps RAW、最大4000nit EVFなど「撮影現場での自由度」を買うならZ6III。成果物の幅と時短で回収できる人に向きます。旅行・家族・ポートレート中心で動画は時々、というならZ5IIがベストバイ候補。N‑RAWをSDで運用できる手軽さも効きます。
サイズ/重量と携行性
Z6IIIは約760g、Z5IIは約700g。日常携行はZ5IIが軽く、グリップは両機とも深めで安定。遠征や三脚移動が多い人は、合計重量やバッテリー・カードの持ち方まで含めて最適化すると満足度が上がります。
競合機との位置づけ:ソニー/キヤノンと比べてどうか
動画と連写でみるとZ6IIIは同価格帯の中心的存在。α7C IIは4K60pがSuper35mmクロップ、R6 Mark IIは静止画良好ながら動画/連写仕様はZ6IIIに譲る場面がある一方、価格面では拮抗。Z5IIは「コスト最適化しつつ最新AFとN‑RAW」を押さえた独自の立ち位置です。
用途別おすすめセッティングとレンズ提案

実用に落とし込む鍵は設定とレンズ。ここでは静止画・動画それぞれで“すぐ効く”組み合わせを挙げます。
人物・旅行・日常
Z5II+Z 40mm F2やZ 24‑120mm F4は軽快で、手ブレ補正と高感度の粘りで夜スナップも安心。Picture Controlの呼び出しをショートカットに割り当て、JPEG納品の手戻りを抑えましょう。
Z6IIIは表示系の見やすさでポートレートのMF微調整がラク。Imaging Cloudのレシピ活用で現場の色作りと後処理の時短を両立できます。
スポーツ・野鳥・Vlog
スポーツ/野鳥はZ6III+CFexpressでプリキャプチャ併用。AFエリアをワイドC1/C2⇄3Dで切り替えると安定します。VlogはZ5IIのN‑RAW(SD内部)で軽装・低コスト運用が現実的。NDと音声まわりを整えると見栄えが一気に上がります。
あなたに刺さるのはどっち?
“価格差が何に効くのか”を言語化すると、Z6IIIは「速度・動画・表示」でプロ寄りの余裕、Z5IIは「静止画中心の高コスパ・軽量・SDで回せる運用」で応えます。共通して-10EV AF、プリキャプチャ、優秀なIBISを備え、どちらも“外しにくい”選択肢です。
Z6IIIがハマる人
動画案件が定期/高速動体が多い/電子シャッター運用を増やしたい/EVFの見えを重視—こうした要件が複数当てはまるなら投資価値は大きいでしょう。
Z5IIがハマる人
旅行・家族・ポートレート中心/動画は時々/総額を抑えてレンズに配分したい。デュアルSDとN‑RAW内部記録は、軽装・少人数チームにとって現実的で強力です。
Z5IIとZ6IIIの比較まとめ
Z6IIIは「部分積層センサー×CFexpress×6K/4K120p×高品位EVF」で“撮れる範囲とスピード”を押し広げるハイブリッド中核機。Z5IIは「EXPEED 7×デュアルSD×N‑RAW内部」で“静止画主体の現実解と低ランニングコスト”を提示します。動画・動体が多い人はZ6III、旅行・人物中心でコスパ重視はZ5IIが幸せになれる選択。
こちらの記事もおすすめ

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント(X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。
あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨
みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!




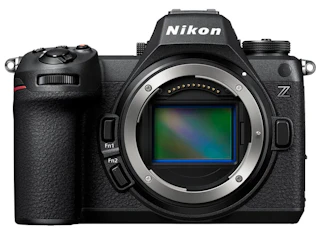



.jpg?fm=webp&q=75&w=640)
.jpg?fm=webp&q=75&w=640)
