
【保存版】カメラの飛行機持ち込みマニュアル 手荷物制限・預け入れ対策までチェック
大事な一眼レフやミラーレスを持って飛行機に乗るとき、「カメラは機内持ち込みでいい?」「国際線でもバッテリーは大丈夫?」「ANAやLCCだとルールは変わる?」と不安になる点が多いですよね。この記事では、カメラの飛行機持ち込みに関する基本ルールから、手荷物と預け入れの線引き、国際線での注意点、ANA・JAL・LCCでの違い、さらにはカメラを飛行機に預ける必要がある場面での対処までをまとめました。
この記事のサマリー

カメラやレンズは基本的に機内持ち込みとし、預け入れは「どうしても」の場合に限定してリスクを下げることが重要。

ANA・JALとLCCでは手荷物のサイズ・重量ルールが大きく異なるため、フライトごとに公式情報を確認して機材量を調整する必要あり。

リチウムイオンバッテリーや三脚などの周辺機材には国際的な規制があり、予備バッテリーは機内持ち込み・三脚は長さ制限などを必ず守る必要あり。

保安検査をスムーズに通るには、カメラやレンズ・バッテリー類を取り出しやすくまとめておき、X線検査で怪しまれないパッキングを意識することが有効。

旅の目的に合わせて「本当に使う機材」に絞り込み、手荷物と預け入れを賢く使い分けることで、安全かつ快適にカメラと一緒に空の旅を楽しめます。
カメラは「飛行機の機内へ持ち込み」が基本

最初に押さえておきたい基本は、カメラやレンズは「預け入れ」より「機内に持ち込む」が原則という点です。精密機器かつ高額な道具なので、衝撃や紛失のリスクをできるだけ減らしたいところ。ここでは、なぜ機内持ち込みが推奨されるのか、そして手荷物として持ち込むときの考え方を整理します。
精密機器は預け入れに向いていない
預け入れ手荷物は、どうしてもベルトコンベヤーや仕分けの工程で大きな衝撃を受けがちです。スーツケースが立てられたり重ねられたりする場面も多く、カメラボディや交換レンズには負担がかかります。内部のガラスや電子部品は繊細で、外装に目立った傷がなくても、ピントずれや動作不良につながる可能性があります。
さらに、ロストバゲージや中身の盗難リスクもゼロではありません。特に海外経由のフライトでは、預けた荷物が別の空港に送られてしまう事例が一定数あります。手荷物としてカメラを機内持ち込みにしておけば、到着後すぐ撮影に移れるだけでなく、トラブル時の精神的な負担も小さくできます。
実際に航空会社の約款では、カメラやパソコンなどの貴重品は原則として「手元で管理すること」を推奨しているケースが多く見られます。補償額にも上限があるため、「壊れても全額戻る」とは考えず、自分で守れる範囲はしっかり守る方針が安全です。
飛行機の手荷物内でのカメラの優先順位
機内持ち込みできる荷物の重量やサイズには制限があるため、「すべてを手荷物に」が難しい場面も出てくるでしょう。そのときは、壊れたら困る順に優先順位をつけると判断しやすくなります。一般的には、撮影データ>カメラボディ>主要レンズ>その他アクセサリーの順で重要度が高くなるでしょう。
SDカードやSSDなどの記録メディアは、たとえ金額が小さくても撮影したカットそのものが入っています。これらは必ず機内持ち込みにし、できれば財布やパスポート同様に常に身につけておきたいところです。カメラの飛行機持ち込みに優先度をつけざるを得ないときは「データと主力機材は手元から離さない」を一つの基準にしましょう。
一方で、小型の三脚や安価なストラップなどは、万が一のときに替えが効きやすい道具です。手荷物の枠が足りなければ、優先度の低いアクセサリーから預け入れに回すイメージで分けると、全体のバランスが取りやすくなります。
航空会社別の手荷物の制限
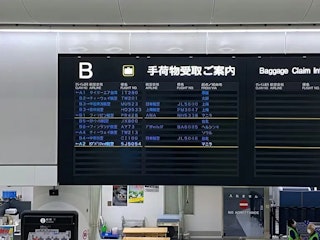
カメラ本体を飛行機の機内へ手荷物として持ち込む際に注意することは、主にサイズと重量についてのみです。
国際線・国内線ともに、日系の多くの航空会社では「手荷物1個+身の回り品1個」「サイズは3辺合計115cm前後」という枠組みが一つの目安になっています。ただし、ANAやJALとLCCでは重量制限が異なります。ここでは、カメラ観点で押さえておきたい代表的なルールを整理しつつ、「どの程度の機材まで持ち込めるか」をイメージしやすくしていきます。海外の航空会社では基準が異なることも多いため、最終的には利用する便の条件を確認しておきましょう。
ANA・JALなどフルサービスキャリアの目安
日本の大手航空会社(ANA・JALなど)では、座席数100席以上の機材を利用する場合、機内持ち込み手荷物の上限は「手荷物1個+身の回り品1個で合計10kg以内」、手荷物1個あたりのサイズは「3辺の合計115cm以内・55×40×25cm以内(ハンドルやキャスター含む)」という基準が共通しています。
項目 | 規定内容(ANA・JAL共通:100席以上) |
|---|---|
持ち込み可能個数 | 手荷物1個 + 身の回り品1個(合計2個) |
重量制限 | 2個の合計が 10kg以内 |
手荷物サイズ上限 | 3辺合計 115cm以内 |
3辺の目安 | 55cm × 40cm × 25cm以内(キャスター・取手含む) |
ここでいう手荷物には、キャリーバッグなどのメイン荷物と、カメラバッグや小さなリュックといった身の回り品が含まれます。座席数100席未満の小型機では3辺合計100cmまでに制限されるケースもあるので、カメラの機内持ち込みをANA やJALで想定する場合でも、自分が乗る便の条件を確認したうえで、この10kg枠をどう使うか考えると安心です。
例えば、機内持ち込みサイズのスーツケースに着替えやPCを入れ、別にカメラバッグを肩掛けするスタイルなら、「2個までOK」の条件を満たします。そのうえで、2つの荷物の総重量が10kgを超えないよう調整すれば、フルサイズ機+標準ズーム+望遠ズーム+ノートPCくらいまでなら十分現実的です。
機種やクラスによって細かな違いはあるため、最終的には利用する便のページで確認する必要がありますが、「10kg・115cm・2個」が一つの基準として役立ちます。特にカメラ関連の手荷物を多めに持ち込みたい場合は、フルサービスキャリアを選ぶと余裕が生まれやすくなります。
LCCで気をつけたい7kgルール
PeachやジェットスターなどのLCCでは、無料で持ち込める手荷物の上限が7kg前後に設定されていることが多くなっています。ここに機内持ち込みサイズのキャリーバッグとカメラバッグを両方含めるとなると、機材を絞り込まないとすぐにオーバーしてしまうでしょう。
項目 | LCCで多いケース(Peach / Jetstar Japan / スプリング・ジャパン) |
|---|---|
持ち込み個数 | 手荷物1個 + 身の回り品1個(合計2個まで) |
重量制限 | 合計7kg以内(航空会社により8kg前後のケースもあり) |
サイズ上限 | 3辺合計 115cm以内 |
3辺の目安サイズ | 55cm × 40cm × 25cm以内(機内持ち込みスーツケース基準) |
最近は、追加料金を払うことで10〜14kgまで機内持ち込み枠を拡張できるオプションを用意しているLCCもあります。ロケや撮影旅行でどうしても機材が多い場合は、チケット予約時にこうしたオプションを検討しておくと安心です。そのうえで、「絶対手元に置きたいカメラとレンズ」「預けても仕方ないアクセサリー」を分けておきましょう。
また、LCCではチェックインカウンターや搭乗口で重量チェックが行われる頻度も高めです。ギリギリを狙うと、思わぬ追加料金や預け入れへの振り替えを求められることがあります。余裕をもって6kg前後に収めるつもりでパッキングすると、ストレスが減ります。
いずれの場合でも事前に、自分の予約プランごとの規定を確認しておきましょう。
バッテリー・三脚・周辺機材のルール
カメラ本体は多くの人が機内持ち込みを意識していますが、忘れがちなのがバッテリーや三脚などの周辺機材です。リチウムイオン電池には国際的な規制があり、扱いを誤るとチェックインカウンターで止められることもあります。ここでは、カメラ機材ごとのルールを整理し、トラブルを避ける準備をしていきましょう。
予備バッテリーは「必ず機内」かつ容量チェック
カメラ用のリチウムイオンバッテリーやモバイルバッテリーは、基本的に「預け入れ不可・機内持ち込みのみ」がルールです。預け入れ荷物に入れてしまうと、X線検査やチェックイン時に取り出しを指示される場合があります。カメラを飛行機に持ち込む際は、予備電池もまとめて手荷物に入れる前提で計画した方が安全です。
容量に関しては、100Wh以下の小型電池なら比較的自由に持ち込める一方、100Whを超えて160Wh以下のものは個数制限が設けられているケースが多くなっています。シネマカメラ用の大型バッテリーなど、160Whを超える電池はそもそも持ち込みできないこともあるため、型番からWh表示を確認しておきましょう。
端子がむき出しのままだとショートの危険があるため、テープで保護したり、専用ケースに入れたりするのも大切なポイントです。透明なポーチにまとめておくと、保安検査で見せてほしいと言われたときもスムーズに対応できます。
三脚・一脚は「長さ60cm前後」が目安
三脚や一脚は、折りたたんだ状態での長さがポイントになります。例えばANAでは、「折りたたみ時の長さが60cmを超える三脚・一脚は機内持ち込み不可」と案内されており、それ以上の長さのものは預け入れ対象になります(国内線・国際線共通)。飛行機手荷物に三脚を入れたい場合は、この60cm前後の基準を満たすトラベル三脚やコンパクトなモデルを選び、利用する航空会社ごとのルールもあらかじめ確認しておくと安全です。
バッグの外側に固定する場合も、折りたたみ時の全長が各社の基準(ANAの場合は60cm)を超えると、搭乗口で預け入れへの変更を求められる可能性があります。雲台を外して短くする、脚を縮め切った状態で固定するなど、全長を抑える工夫をしておきましょう。どうしても大きな三脚を使いたい場合は、クッション材を詰めたケースに入れて預け入れに回すのが現実的です。
国内線と国際線で違うポイント

国際線と国内線では、手荷物サイズや重量よりも、保安検査や液体ルールの違いが効いてきます。また、乗り継ぎで複数の航空会社を利用する場合、それぞれの規定が絡み合う点にも注意が必要です。ここでは、海外フライトでカメラを運ぶときに意識したいポイントを整理します。
液体ルールとクリーニング用品
国際線では、機内に持ち込める液体の量に制限があります。多くの国・地域の空港では、100ml以下の容器に入れた液体を1リットル以下の透明袋にまとめるルールが採用されています(日本発の国際線もこの方式が基本です)。レンズクリーナーや液体タイプのブロアーなどを持ち込む場合は、このルールに沿って準備しておきましょう。なお、欧州の一部空港などではCTスキャナー導入により制限が緩和されつつあるため、出発空港ごとの最新情報も確認しておくと確実です。
スプレー缶タイプのクリーニング用品は、そもそも機内持ち込みや預け入れが禁止されている場合もあります。事前に使い切っておくか、旅先で購入する前提に切り替えた方が安全です。ウェットティッシュタイプのレンズクリーナーなら、液体扱いにならないケースもあるため、代替品として活用できます。
日本の国内線では、国際線のような100ml/1リットルのルールはなく、飲料などは1容器500ml・総量2リットルまでといった比較的緩やかな基準が空港ごとに設けられています。一方、海外からの復路では国際線と同様に100mlルールが適用されるのが一般的です。行きと帰りで同じように持てるとは限らないので、「国際線の基準に合わせておく」と考えて準備すると、余計な買い直しを減らせます。
乗り継ぎ時の航空会社ごとの違い
海外旅行では、往路と復路で別の航空会社を使ったり、途中の乗り継ぎで現地の航空会社に切り替わったりすることがあります。その場合、機内持ち込み手荷物のルールは、最も厳しい会社の基準に合わせておくのが安全です。行きはANAやJALでゆったり10kg持ち込めても、乗り継ぎ先の会社が7kgまでしか認めていないことも珍しくありません。
カメラの飛行機持ち込みを計画するときは、「全区間を通して手荷物ルールを確認する」ことが大切です。予約サイト上で表示される情報だけでなく、各社の公式ページもチェックしておくと安心度が上がります。特に海外LCCは、重量超過に対して料金がシビアに設定されている場合が多いので注意が必要です。
保安検査をスムーズに通過するコツ

カメラの飛行機持ち込みで意外と緊張するのが、保安検査場です。ノートPCや液体と同じく、カメラ機材にもいくつかのルールがあります。ここでは、検査で止められにくいパッキングと、スムーズに通過するための小さな工夫をまとめます。
カメラやレンズは取り出しやすくしておく
空港によっては、ノートPCと同様にカメラボディや大きなレンズをカバンから取り出してトレイに載せるよう求められることがあります。バックパックの奥深くに詰め込んでいると、そのたびに大きな荷解きをすることになり、列を詰まらせてしまいがちです。
検査場を通るときだけ、カメラを上の方の仕切りに入れておく、もしくはインナーボックスごと取り出せる構造のバッグを使うと、作業がかなり楽になります。レンズも、大きなものは1〜2本に絞り、必要ならトレイに出せるようまとめておきましょう。
バッテリーやケーブルを整理して見せる
カバンの中にバラバラにバッテリーやケーブルが入っていると、X線画像上で判別しにくくなり、追加検査の対象になりがちです。予備バッテリーはポーチにまとめ、ケーブル類も1セットずつ束ねておくと、検査員から見ても状況が把握しやすくなります。
リチウムバッテリーについて確認されたときに備え、端子をテープで保護している様子を見せられるようにしておくと安心です。「適切に管理している」と判断されれば、その後のやりとりも短時間で済むことが多くなります。
カメラを預ける必要があるときの対策

カメラは原則飛行機への持ち込みと意識していても、機材量やLCCの制限によって、一部を預けざるを得ない場面は出てきます。そのときに何も考えずにスーツケースへ放り込んでしまうと、到着地で思わぬトラブルに直面するかもしれません。ここでは、「どうしても預けるしかない」ときのダメージ軽減策を整理します。
本体とレンズは分けて厚く保護する
ボディとレンズを装着したまま預け入れ荷物に入れると、衝撃がマウント部に集中しやすくなります。預ける場合は、必ずレンズを外し、それぞれにキャップを装着してから梱包しましょう。レンズは厚手の衣類やタオルで二重三重にくるみ、ハードケースがあればその中に入れると安心度が上がります。
スーツケース内では、機材が動かないよう隙間を埋めることが大切です。四方と底面に服を敷き詰め、その上に機材を載せ、さらに上から衣類で挟み込むイメージで固定します。ケースの中でガタつきがなければ、ベルトコンベヤーの衝撃もかなり緩和できます。
防湿剤を一緒に入れておくと、結露や湿気対策としても有効です。長時間のフライトや乗り継ぎで気温差が大きい路線では、こうした細かな対策が後々の安心につながります。
バッテリーと記録メディアは必ず抜き取る
カメラを飛行機に預ける判断をするとき、忘れてはいけないのがバッテリーと記録メディアの扱いです。バッテリーは前述のとおり機内持ち込みが原則であり、預け入れ荷物に残したままにしないよう注意が必要です。機材からバッテリーを抜き、端子を保護したうえで手荷物のポーチにまとめておきましょう。
またSDカードやCFexpressカードなどの記録メディアも、必ず手元に持っておきたいアイテムです。撮影したデータはお金では買い戻せないため、最優先で守るべき対象になります。可能ならクラウドや外付けSSDへバックアップを取り、データのコピーを複数確保しておくとさらに安心です。
カメラの飛行機持ち込みについてのまとめ
カメラの飛行機持ち込みを安心して行うには、
- 精密機器は基本的に機内へ
- 予備のリチウムイオンバッテリーは必ず手荷物に
- 航空会社ごとの重量とサイズの基準を事前に確認
の3点を軸にするのが有効です。そのうえで、ANAやJALなどフルサービスキャリアとLCCで手荷物枠が大きく違うことを踏まえ、どこまでを機内手荷物として持ち込み、どこからを預けるかを決めていきましょう。次にフライトを予約するときは、利用する会社の手荷物ページと、自分が持っていきたい機材リストを並べてチェックしてみてください。優先順位を整理し、パッキングと保安検査の流れをイメージしておけば、大切なカメラと一緒に、より気持ちよく空の旅を楽しめるはずです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。
あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨
みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!



.jpg?fm=webp&q=75&w=640)

.jpg?fm=webp&q=75&w=640)