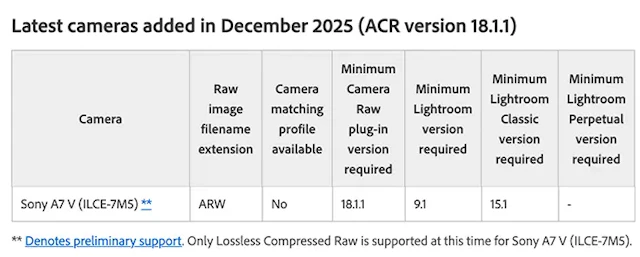.jpeg?fm=webp&q=75&w=1152)
【リーク】Light Lens Lab 300mm f/1.9 APOの発売日はいつ?価格予想・比較・予約まとめ
Light Lens Labにより開発中とされる300mm f/1.9 APOのリーク情報は、中判センサー対応・MF想定という異例尽くしの情報で注目を集めています。本記事ではメーカー未発表の事項は未確定として切り分けつつ、発売日・予約・価格・スペックの予想、既存300mm F2.8や200mm F2との比較までをまとめました。
この記事のサマリー

LLL 300mm f/1.9 APOは開発中で、中判センサーをカバー予定とするリーク情報あり

発売日・価格・対応マウントは未公表。MF専用の見込みは報道ベースで公式未発表。

F1.9は300mm F2.8比で約2.2倍の入射光量。被写界深度は極薄で背景分離が強い。

比較軸:現行300mm F2.8群、Laowa 200mm F2 AF。
リークの要点をまず把握
.jpeg?w=320)
中判カバーの300mm f/1.9、APO設計という骨子が複数媒体で報道されています。発売日・価格・マウントは未発表のままです。
確認できる事実
Photo Rumorsにて、Light Lens Labが300mm f/1.9のAPO設計レンズを開発中で、中判センサーをカバー予定とする報道がされています。Photo Rumorsは巨大な前玉の写真やテスト生産の動画も掲載していますが、メーカーの正式発表や製品ページは未公開であくまで情報は開発中・リーク情報段階です。
「現代の300mmにおける最速開放は通常F2.8」という相場観に対して、F1.9は約1段強の明るさ増です。光量差だけでなく表現レンジが大きく変わる可能性があり、注目に値します。
未確定項目
発売時期・価格・対応マウントは未公表です。Imaging ResourceでもLight Lens Lab 300mm f/1.9 APOについて言及されており、“マニュアルフォーカスのみ”とする噂の仕様も記載していますが、いずれの仕様もメーカーの正式発表ではありません。公式告知や展示情報の確認までは未確定事項として扱うのが妥当です。
スペック要点と読み方:F1.9・APO・中判対応を把握
リーク段階でも、撮影者が“いま”押さえておくべき技術的ポイントは整理できます。F1.9の光量、APOによる色収差対策、中判対応によるイメージサークルの余裕。これらは機材選定・セットアップ・現場オペの意思決定に直結します。
F1.9という明るさ:露出と表現幅に効く
F1.9は300mm F2.8比で約2.2倍の入射光量です。シャッター速度を約2.2倍稼ぐか、ISOを約1/2.2に抑えるか、あるいは両方の中間を取る運用が可能。被写界深度は極薄で、背景分離は一段と強力になります。ここは“速度・ノイズ・質感”の優先度で配分を決めましょう。
ただし薄いピント面は歩留まりの壁にもなります。AFではなくMF想定のため、拡大確認とピーキングを併用し、撮影側の調整リソースを十分に確保すると安定します。
APO設計×中判カバーの意味
APOは軸上色収差・倍率色収差の抑制を狙う設計思想で、ハイコントラスト域でも色滲みを最小化しやすいのが狙い。中判カバーはイメージサークルに余裕があるぶん、フルサイズ運用でも周辺特性の確保に寄与する可能性があります。
Imaging Resourceは100MP級中判でのシャープネス維持に触れています。量産実機でどこまで実現されるかは未確定ですが、「解像と色収差の両立」を強く志向する設計方向が予想されます。
巨大前玉と取り回し:物理サイズを“数字で”見積もる
入口瞳は焦点距離÷開放F値。300÷1.9≒158mmが理論値で、実機の前玉はこれ以上の径になることが一般的です。重量・重心・支持機材に直結するため、運用は“据え置き前提”の準備が鍵になります。
前玉径から逆算する現場要件
158mm級の前玉はフード・フィルター・ケースの全てを大径仕様に引き上げます。衝撃・粉塵・温度変化の影響も大きく、従来の300mm F2.8用アクセサリーではサイズが合わない可能性が高いでしょう。まずは運搬と保護体制の設計が必要です。
Photo Rumorsにはテスト生産とされる前玉の写真・動画が掲載されています。視覚情報としてスケールが分かるため、収納・現場スペースの見積もりに役立ちます。三脚座の強度や雲台の耐荷重も、先に“数字”で当たりを付けておくべきです。
支持機材の基準値を用意する
脚は伸縮時の撓みが少ないシステマチック三脚、雲台は荷重域に余裕のあるフルードまたはギア雲台を推奨。レンズフットはアルカ互換の長尺でバランス調整幅を確保し、縦横切替時の安定性を担保しましょう。
現場での安全は“落下させない”に尽きます。クランプの締め忘れ防止、運搬時のレンズ側面保護、車載時の固定ポイントなど、チェックリスト化して習慣に。機材保険の適用範囲も事前確認しておくと安心です。
フォーカス運用:MF前提で歩留まりを上げる実践セットアップ
報道レベルではMFのみの可能性が指摘されています。被写界深度が極薄な300mm F1.9で歩留まりを安定させるには、拡大表示・ピーキング・フォーカスリミッター的運用の三本柱を押さえます。素早さより再現性を優先しましょう。
精密合焦の基本ワークフロー
ライブビュー拡大で眼球や睫毛など高周波領域に合わせ、ピーキングは過敏設定を避けて“山の頂点”を見極めます。被写体が動く場合も、意図的に合焦位置を前後に揺らし複数ショットで拾うのが合理的です。
三脚運用時はミラーショックのないボディでもシャッターショックや風の影響は無視できません。電子先幕や静音モード、高速シャッターの併用で微ブレを削り、撮影リズムは「止めて・確認して・次へ」を徹底しましょう。
プリフォーカスとレンジ管理
背景分離を強く出せる一方、少しの被写体移動でアウトフォーカスになりがちです。目標距離を決め、そこに入った瞬間のみ切る“ゲート運用”が有効。舞台やランウェイの定点撮影と相性が良好です。
リング操作は小刻みより“粘る”イメージで。フォローフォーカスを用いれば微調整の再現性が上がります。スライダーやドリーと併用する場合は、被写界深度と移動速度のバランスを先に決めてから構図を詰めましょう。
中判カバーの実務:GFX・X2D系で意識したいポイント
GFXやX2D IIなど100MP級での使用が想定されるなら、合焦精度・微ブレ対策・周辺特性のチェックは必須です。テザー撮影や現場確認の導線を事前に固め、撮影後の選別時間も見積もっておきましょう。
100MP級での画質確認プロトコル
被写体中心・周辺・四隅でピント・コントラストを確認し、構図ごとに基準ショットを残します。天候や温度差で描写が変化する可能性があるため、同一設定での比較素材を現場で作っておくと後工程が早まります。
APO設計が色収差・フリンジを抑える想定でも、逆光や強い点光源は検証対象。NDや黒ケント紙で不要光を抑え、ゴーストの出方を把握。GFX系ではピクセルシフトの併用も念頭に置き、動体を除く被写体で“静的高解像”を狙いましょう。
マウント未発表期の準備
対応マウントは未確定です。アダプターでの回避を想定するなら、フランジバック差・干渉リスク・重量物の支え方を先に学習しておくと安心です。特に中判ボディはマウント面の負荷に配慮しましょう。
ボディ・レンズ・アダプターの三点を別々に支える“デュアルサポート”を検討。L字ブラケットとロングプレートでバランスを取り、ケーブル類のテンションをゼロに近づければトラブルが減ります。
比較①:現行300mm F2.8との違いを“現場の選択”に落とし込む
一般的な300mmはF2.8が最速で、AF・手ブレ補正を備えた完成度が魅力です。対してF1.9は光量と描写の極みを狙う性格。用途・現場条件・仕上げの理想像で選び分けるのが合理的です。
明るさと露出裁量の差
夜間スポーツや屋内舞台で、1段強の余裕はシャッター速度かISOのどちらかを確実に助けます。ボケ量も一段深く、背景処理の主導権を握りやすいのが利点です。絵作りを優先する案件で強みが出ます。
一方で歩留まり・速度・機動力はAF搭載のF2.8に軍配。高速連写や被写体追従が重要な現場では、安定運用を優先する選択が現実的です。F1.9は“刺さるシーンで刺す”尖った道具と捉えましょう。
重量・運用とチーム体制
F1.9の機材スケールは雲台・脚・運搬を含めて一段上の準備を要求します。撮影補助者の有無、設営時間、撤収導線まで含めた体制設計が鍵。スチルとムービーを同時に回す現場では特に差が出ます。
AF・ISの恩恵が不要な案件、例えば定点のファッション・プロダクト・ポートレートなどでは、F1.9の“絵の圧”にリソースを集中。タスク分配で弱点を潰す発想が成果に直結します。
比較②:200mm F2や最新“明大口径”の動向を押さえる
超望遠で“明るさ”を追う潮流は加速中です。直近ではVenus Optics(LAOWA)がAFの200mm F2を正式発表し、価格と重量の面で実用的な水準に引き寄せました。300mm F1.9はさらに異質ですが、同カテゴリの期待値を一段押し上げています。
こちらの記事もおすすめ

Laowa 200mm F2 AFの示唆
AF対応・比較的コンパクトは、明大口径を実用的な水準に引き寄せました。大口径が特別用途だけに留まらないというメッセージは、機材選定の基準を更新します。
もっとも300mm F1.9は別次元のスケールです。Laowaの成功が示したのは、中国勢が量産と品質を両立できる可能性です。LLLの件も、価格や供給の読みで過度な悲観や楽観に偏らない視界を持てるでしょう。
既存選択肢との住み分け
200mm F2はポートレートや室内スポーツで万能。300mm F1.9はより強い圧縮とボケで“唯一無二”を狙う立ち位置です。シーンの要件に応じ、機動力・AFの必要性・表現の尖り方で住み分けましょう。
量産入手性・メンテ網・再販価値など、総保有コストの視点も重要です。複数本のシステムで使い回すほど投資回収は進みます。
システム設計:ボディ・アダプター・サポート機材の整合を取る
対応マウント未発表期は“仮説運用”の設計が要です。中判ボディのフランジバック・アダプターの強度・レンズフットの互換性を先に検討し、重量物の一体支持を最優先に据えましょう。
中判ボディの負荷対策
マウント面だけで支えない発想が基本。ボディ側Lブラケット+長尺プレート+レンズフットの二点保持でモーメントを逃がします。ヘッドのクランプはロングタイプにして調整域を広げると安定します。
テザー撮影時はケーブルテンションをゼロに近づけ、抜去方向に力が掛からない配線に。現場移動が多い場合、簡易カートやショックマウントの導入で機材疲労を抑え、再現性を担保します。
まとめ
Light Lens Lab「300mm f/1.9(APO)」は、中判カバー・F1.9・APOという要素が重なる“超ヘビー級”。一方で発売日・価格・マウントは未発表で、購入判断は続報待ちが現実的です。現段階でできることは、明るさの使い道を具体化し、MF・支持機材・安全運用の準備を前倒しすることです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント(X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube)で毎日発信中。
あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨
みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!



.jpg?fm=webp&q=75&w=640)