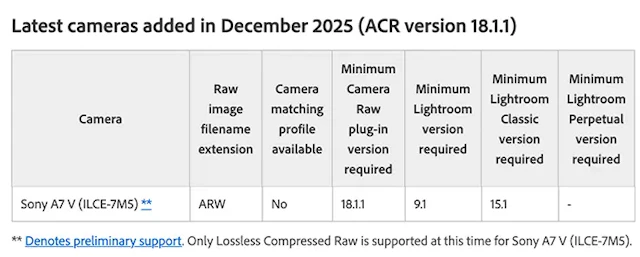.webp?fm=webp&q=75&w=1152)
測光モードの使い分けガイド。評価・中央重点・スポットの違いとは
逆光で顔が真っ暗、雪景色が灰色に…そんな露出の悩みは、測光モードの見直しで防げます。この記事は測光モードの使い分けとして、評価・中央重点・スポット・ハイライト重点の「どれを、いつ、どう使うか」を整理しました。
この記事のサマリー

測光モードは「どこを基準に明るさを決めるか」を指定する設定。

評価測光は汎用性が高く、基本はここから。逆光などで外れたら切り替える。

中央重点は主役が中央付近のとき有効。少ない補正で狙いに届きやすい。

スポットは明暗差が極端なシーンで一点基準に。AEロック併用で安定。

ハイライト重点は白飛び回避を優先。暗部は露光量や後処理で補う。
測光とは
.webp?w=320)
測光モードの話に入る前に、まず測光とは何かは把握しましょう。測光とは、カメラが被写体からの反射光を測定して、適正露出(シャッター速度・絞り・ISOの組み合わせ)を決めるための明るさ計測のことです。
測光モードとは?「どこを基準に明るさを決めるか」
測光モードは「画面のどのエリアの明るさをどの比率で参考にするか」を決める設定のことです。明るさの基準点が変われば、同じシーンでも仕上がりが変化します。
どこを基準にして明るさを決めるか定める測光モードには、評価測光・中央重点測光・スポット測光・ハイライト重点測光の4種類があり、この記事ではそれぞれの特徴や注意点も紹介していきます。
測光の基本:18%グレーを意識する
多くの内蔵露出計は被写体の反射光を基に、シーンを中間反射(おおよそ12〜18%相当のグレー)に近づけるように働きます。真っ白な雪原は暗く、真っ黒な被写体は明るく出やすい傾向はこの特性に由来します。仕組みを理解すれば対処は容易です。
測光モードは、この「平均の取り方」を変えるスイッチだと捉えると理解が速いです。全体を見るか、中央重視か、一点だけを測るか。選択で露出の優先順位を明示できます。
実際の現場では、測光モードに露出補正を組み合わせて調整します。基準を決め、補正で仕上げる二段構えが安定の近道です。
よくある失敗とモード選択の関係
逆光で人物が暗いのは、明るい背景に平均が引っ張られるため。中央重点やスポットに切り替えると改善します。雪やウエディングの白飛びは、ハイライト重点が有効です。
夜景でネオンが白く潰れやすいのは、暗部の面積が広く平均が持ち上がるためです。スポットで光源を測れば、濃い色と質感を残しやすくなります。全体を守るか、主役を守るか、優先を決めましょう。
測光モードの種類別サマリ
詳しく紹介する4つの測光モードの特徴早見表です。
モード | 測光の基準・範囲 | 向いているシーン | 主なメリット | 注意点・弱点 |
|---|---|---|---|---|
評価測光(多分割) | 画面全体を複数エリアに分割し総合判断 | 旅行スナップ、風景、動体など“まずこれ” | バランス良く外しにくい/連写や場面変化に強い | 逆光や極端な明暗差では主役が暗くなりやすい |
中央重点測光 | 画面中央に重みを置き周辺は補助 | 商品・料理、バストアップ、主役が中央の構図 | 主役の露出を安定させやすい/少ない補正で決まりやすい | 主役が中央から外れると露出ブレ/強い光源が中央に入ると不安定 |
スポット測光 | 画面のごく小領域(1〜3%程度)だけを測る | 逆光ポートレート、舞台、月・ネオンなど高コントラスト | 一点の明るさに厳密に合わせられる/主役最優先 | 位置ズレに弱い/全体バランスが崩れやすい(AEロック併用推奨) |
ハイライト重点測光 | 最も明るい部分を優先して白飛びを抑制 | ステージ、白無垢・ウェディング、金属・ガラス反射 | 白飛びを避けやすく質感を残せる | 暗部は沈みがち→露光量確保や後処理が必要/対応機種限定 |
測光モード①評価測光:まずはこれ。バランスで外しにくい
.jpg?w=320)
フレームを細かく分割し、全体の明るさやコントラストから露出を出す万能型。評価測光 = 多分割測光といわれることもあります。
旅行スナップや均一な風景、動体撮影など、状況が変わる場面でも安定しやすいのが強みです。「まずは評価測光で、困ったら切り替え」が運用上の起点として有効です。よく撮るシーンごとに定番モードを決めておくと判断が速くなります。
得意な場面と設定のコツ
明暗差が大きすぎない屋外、街歩き、日中のポートレートで安定します。測光は評価、露出補正は±0を起点に、ハイライトが気になるときだけ−0.3に振ると安全です。
対応機種では、評価(マルチ)測光時に顔優先AEなどが働き、検出した顔や瞳に露出が寄る場合があります。背景の輝度に引っ張られにくく、肌トーンの再現に寄与します。
連写時も露出が暴れにくいのが利点です。シャッターチャンスを優先したいときほど、評価測光の安定感が効きます。
つまずきやすいポイント
逆光や窓辺など、画面の一部だけ極端に明るいと主役が暗くなります。そんなときは思い切って中央重点やスポットに切り替える判断が必要です。
白い衣装や雪景色では「灰色寄り」に寄る傾向があります。+0.7前後の補正で白さを取り戻すと質感が出ます。ヒストグラムで右端の張り付きを避けつつ微調整しましょう。
夜景は暗部が多く、過剰に明るくなりがち。−0.7~−1.0の補正で黒を締めると、色が濁らず抜けが良くなります。
測光モード②中央重点測光:主役を真ん中に置くと強い
フレーム中央の明るさに重みをかけて露出を決める方式です。商品・料理・バストアップなど、主役を中央付近に据える構図で安定しやすくなります。
人物・物撮りで安定させる
.webp?w=320)
白背景のブツ撮りや逆光ポートレートでも、中央にある被写体の露出を優先できます。評価で暗く転ぶ場面でも、中央重点にすると肌の階調が出やすくなります。
背景の明るさが変わるロケでも、主役の見た目を一定に保ちやすいのが長所です。色や素材の再現を重視する用途で有効です。
主役が中央から外れると露出がぶれます。構図を決める前にAEロックで露出を確保すると、狙い通りの仕上がりに近づきます。
露出補正の合わせ技
白い皿や純白ドレスは+0.3~+1.0で白を守る。黒い被写体は−0.3~−1.0で締める。中央重点は少ない補正で狙いに届きやすいのが特長です。
スタジオの連続光や窓辺の柔らかい光では、中央重点+固定WBが安定します。色温度が変わらず、後処理の手間も減らせます。
被写体を中央に置けない構図は、中央重点を避けるかAEロックで回避。測る→ロック→構図の順が有効です。
測光モード③スポット測光:一点主義で逆光を制する
.webp?w=320)
フレームのごく小さな範囲だけを測って露出を決めます。逆光の顔、舞台のスポットライト、月やネオンなど、明暗差が極端な場面で有効です。
狙う場所を決めると成功する
頬や額など、出したい明るさを持つ部位にスポットを合わせます。背景がどれほど明るくても、主役の露出を優先できます。
測る位置がずれると露出が外れます。AFポイント連動のスポット測光が使える機種なら、ピント位置と露出の一致を取りやすくなります。
肌を基準にするときは+0.3前後を起点に調整。黒服など濃色を基準にするなら−補正を加えると階調が整います。
AEロックと組み合わせる
測る→AEロック→構図の手順を徹底すると安定します。スポットで拾った露出を固定したまま、自由にフレーミングできます。
連写や動体では、測る位置が動くと結果が揺れます。先に露出を固定してから追従AFに集中すると歩留まりを保ちやすくなります。
ネオンや月は明るい部分を基準に−補正を加えるのが一般的です。質感を残しつつ、黒を黒として描けます。
測光モード④ハイライト重点測光:白飛びを優先的に守る
.webp?w=320)
画面内で最も明るい領域を優先して露出を決定し、白飛びを避けやすくする設計です(対応機種)。ステージ撮影、白無垢、強い反射をともなう金属やガラスなどで有効です。
舞台・スポットライトで強い理由
通常の平均では明るい顔が飛びがちでも、ハイライト重点なら白を基準に抑えられます。肌の艶や衣装の光沢を残しやすく、後処理での持ち上げにも向きます。
暗部は沈みやすいので、露光量を増やす(シャッターを遅くする/絞りを開く/補助光を加える)か、後処理で持ち上げる判断が必要です。ISOを上げてもセンサーに届く光は増えないため、ノイズ低減に直結しません。
被写体が動く舞台は露出の揺れが出やすい場合があります。必要に応じてAEロックやマニュアル露出へ切り替え、安定を優先します。
白・反射素材の質感を残すコツ
ウェディングや商品撮影で白を守りたい場合は、ハイライト重点が近道になりやすいです。テクスチャが失われにくく、編集耐性も高まります。
ガラスやクロームメッキは輝点が極端に明るくなることがあります。輝点に合わせすぎると全体が暗くなるので、−0.3~−0.7で微調整します。
ヒストグラム右端をわずかに空ける意識が安全。警告点滅(ゼブラ・対応機種)が見えたら、1/3段戻すと安定します。
迷わない選び方:シーン別の基準づくり
「まず評価測光、困ったら切替」を主軸に、①明暗差の大きさ、②主役の位置の二軸で選ぶと迷いません。
明暗差で選ぶ
明暗差の状況 | 推奨する測光モード | 特徴・目的 |
|---|---|---|
小さい | 評価測光 | 全体を平均して自然な明るさを得やすい |
中程度 | 中央重点測光 | 主役の露出を安定させたいときに有効 |
極端 | スポット測光 | 一点の明るさを基準に正確に露出を決定する |
白飛び回避が最優先 | ハイライト重点測光 | 最も明るい部分を基準に白飛びを防ぐ |
試写とヒストグラムで確認しながら、必要に応じて切り替えます。迷ったらまず評価で試写し、暗い主役が出たら中央重点かスポットに切り替えます。露出補正は±0.3刻みを起点に小さく積み上げると再現性が保ちやすくなります。
露出を大きく動かさないほど、後処理や連写時のばらつきが抑えやすくなります。
主役の位置で選ぶ
主役の位置 | 推奨する測光モード |
|---|---|
中央付近 | 中央重点測光 |
フレーム端 | スポット測光 |
フレーム端(AF連動対応機種) | スポット測光(AFポイント連動) |
複数人や集合写真は評価が安定。人物認識対応機種では肌の再現がまとまりやすくなります。
主役の動きが速い場合は評価を起点に。測光位置の管理負荷を下げ、成功率を高めます。
メーカー別:名称と設定の“クセ”を押さえる
.webp?w=320)
考え方は共通ですが、メーカーによって測光モードの呼び方が変わります。キヤノンは「評価/部分/スポット/中央部重点」、ニコンは「マルチパターン(マトリクス)/中央部重点(機種により重み範囲や全画面平均の選択あり)/スポット/ハイライト重点」。
名前の違いに惑わされない
ソニーは「マルチ/中央重点/スポット」を基本に、機種によって「全画面平均」「ハイライト」などが選べる場合があります。富士フイルムは「マルチ/中央重点/スポット/アベレージ」を搭載する機種が一般的です。呼び名は違っても、基本的な役割は近い設計です。
スポットがAFポイント連動か中央固定かは機種差があります。メニューに連動設定があればオンにすると運用が簡潔になります。
中央重点の重みづけ範囲を選べる機種(例:一部のニコン機で円直径や全画面平均を選択可能)では、被写体サイズに合わせると失敗が減ります。
カスタムボタンに割り当てる
測光モード切替をボタンに割り当てると、逆光や強い反射に入った瞬間でも素早くスポットやハイライト重点へ切り替えられます。
露出補正ダイヤルの近くに置くと、基準と仕上げを連動させやすくなります。測る→補正の流れが手癖になると撮影が速くなります。
ユーザープリセットに「逆光用」「夜景用」を登録しておくと現場で迷いません。再現性が上がり、編集の揺れも抑えられます。
ポートレート・風景・夜景での測光モード
よく撮る三大シーンを型にしておくと、初動が速くなり判断が安定します。以下は再現性の高い叩き台です。
逆光ポートレートの叩き台
測光はスポットまたは中央重点。露出補正は+0.3~+0.7を起点に、肌をやや明るめに設定。WBは太陽光固定で肌色を一定に保ちます。
設定項目 | 推奨設定 | 意図・目的 |
|---|---|---|
測光モード | スポット測光 または 中央重点測光 | 被写体の肌に正確に露出を合わせ、逆光や明暗差の影響を抑える |
露出補正 | +0.3 ~ +0.7 を起点 | 肌をやや明るめに表現し、自然で健康的な印象に仕上げる |
ホワイトバランス(WB) | 太陽光固定 | 光の色味に左右されず、肌色を一定に保つ |
髪の縁取りにハイライトが出る場合でも、肌の階調を優先する運用が一般的です。背景のハイライトは飛ぶことがありますが、許容範囲を被写体と背景のバランスで判断します。
フレアでコントラストが落ちる場合は、レンズフードや手で迷光を遮ると改善します。
風景の叩き台
測光は評価。空のハイライトを守るため−0.3を足し、雲の立体感を保ちます。WBは太陽光固定で色再現を安定させます。
設定項目 | 推奨設定 | 意図・目的 |
|---|---|---|
測光モード | 評価測光 | 全体の明るさをバランス良く測りつつ、シーン全体の露出を安定させる |
露出補正 | −0.3 | 空のハイライトを守り、雲の立体感や階調を維持する |
ホワイトバランス(WB) | 太陽光固定 | 光の変化に影響されず、自然で安定した色再現を得る |
PLフィルターで反射を整理すると彩度が安定します。遠景の霞は軽い−補正で締めると、抜けが生まれます。
三脚が使えるならISOは最小値、絞りは回折と解像のバランスでF8前後が目安です。
露出ミスの原因とリカバリー術
白飛び・黒潰れ・ばらつきは、測光の基準を見直すと切り分けが容易です。現場でできる対処を持っておくと安心です。
白飛びしたとき
ハイライト警告が点滅したら、まず−0.3~−0.7の補正。評価ならハイライト重点に、中央重点ならスポットで明るい部分を測り直します。
RAWなら復元余地はありますが、完全に飽和した情報は戻りません。現場で守るのが最も確実です。
反射や逆光が原因なら、立ち位置や角度を少し変えるだけで改善することがあります。物理的な工夫も同時に試します。
黒潰れしたとき
スポットで暗部を測り直すか、+0.3~+0.7に補正。評価のまま上げると白が飛ぶなら、測光の基準を切り替える方が近道です。
黒い衣装など主題の色が濃い場合、−補正の戻し忘れに注意します。黒を黒として出すのか、階調を優先するのかを先に決めます。
暗部のノイズが気になる場合は露光量(シャッター/絞り/照明)で稼ぐのが基本です。ISOはシャッター速度確保のための手段として用います。
連写・動体で露出が暴れるときの安定策
背景が頻繁に変わるスポーツや動物撮影は、測光の基準が揺れて露出が暴れがちです。平均を味方にしつつ、必要時だけ狙い撃つ運用が有効です。
安定優先の考え方
評価測光+露出補正固定を起点に、人物・車体などを優先する被写体認識機能(対応機種)と組み合わせます。
明暗が極端なエリアに入る直前だけ、スポットやハイライト重点へ一時的に切り替え。カスタムボタン割り当てが活きます。
連写バッファが深いほど歩留まりの確保につながります。露出の大振りを避け、構図とタイミングに集中します。
ヒストグラム・ゼブラ:メーター以外の“保険”
測光は基準づくり。仕上がりの最終確認は、ヒストグラムとハイライト警告(ゼブラ・対応機種)を併用すると抜け漏れを減らせます。
ヒストグラムの見方を体に入れる
右端が壁に当たっていれば白飛びの可能性、左端なら黒潰れの兆候です。多くの機種では表示はJPEGベースのため、RAW撮影時はわずかに余裕が残る場合があります。
日中の風景は右寄せ、夜景は中央〜左寄せが目安。再生時にヒストグラムを確認し、補正を素早く入れる癖をつけると安定します。
ゼブラ表示を閾値70〜100%などで使い分けると、白飛びの見落としが減ります(対応機種)。
測光モードと露出モードの合わせ方
測光で「基準」を決め、P/A/S/Mで「どのパラメータを自動で動かすか」を決めます。役割を分けると操作が整理されます。
絞り優先・シャッター優先の使い分け
背景ボケを狙うなら絞り優先+評価。動きを止めるならシャッター優先+評価。基準はそのまま、補正で微調整します。
逆光などの難所は、絞り優先+中央重点またはスポットが効率的です。速度ブレに注意しつつ、必要に応じてISOや補助光で支えます。
完全マニュアルは再現性が高い一方、測光の読み解きが必須。ヒストグラムやゼブラと併用し、外れを減らします。
まとめ
測光モードは「どこを基準に明るさを決めるか」を指定する設定です。まず評価モードで全体を整え、逆光や白飛びが気になれば中央重点・スポット・ハイライト重点へ切り替える。基準を決め、露出補正とヒストグラム(必要に応じてゼブラ)で仕上げる流れを手癖にすれば、露出のブレは着実に減らせます。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント(X /Threads /Instagram /TikTok /YouTube )で毎日発信中。
あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨
みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!



.jpg?fm=webp&q=75&w=640)