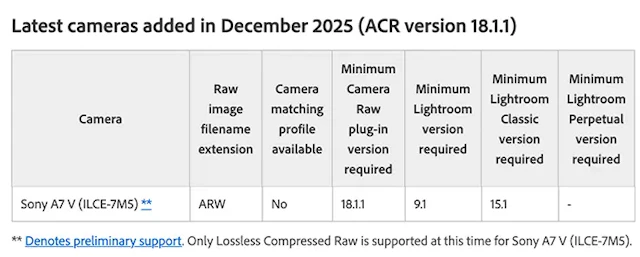【リーク】OM SYSTEM OM‑10の発売日はいつ?開発中止の噂・価格予想・比較・予約まとめ




マイクロフォーサーズのエントリー機の本命として期待されてきた「OM SYSTEM OM‑10」。しかし2025年になっても正式発表はなく、今度は「開発を中止したらしい」という噂まで飛び交っています。「OM‑10は本当に出るの? 待っていていいの?」「E‑M10 Mark IVの後継ってどうなるの?」そんな疑問が多いなか、2025年11月時点の情報を総ざらいしつつ「結局いま何を買うのがベストか」まで一挙に整理します。
この記事のサマリー

OM SYSTEM OM-10が未発表のまま開発中止説まで出ている現状を、2025年11月時点の事実ベースで整理した記事です。

2023年の「OM-10来るかも」初報から、OM-1 Mark II/OM-3/OM-5 Mark II登場によるラインアップ再編までをタイムラインで追います。

噂とインタビューを突き合わせ、「OM-10という型番で出る可能性は低いが、E-M10的エントリー機コンセプト自体は残っている」と結論づけます。

OM-10を待つか悩む読者向けに、E-M10 Mark IV・OM-5 Mark II・OM-1 Mark II/OM-3など現行機からの現実的な選択肢を用途別に提案します。

最後に「OM-10は夢枠として気にしつつ、いま手に入る一台で撮り始めるのがベスト」という行動寄りのメッセージで締めくくります。
【25年11月28日追記】OM SYSTEM OM‑10はいまどうなっている?現状整理

まず現状の事実として2025年11月時点で、OM SYSTEM公式サイトのミラーレス一眼ラインアップに並んでいるのは、
- OM SYSTEM OM‑1 Mark II
- OM SYSTEM OM‑3
- OM SYSTEM OM‑5 Mark II
といったモデルで、「OM‑10」という名前のカメラは掲載されていません。
一方で、2025年8月に43Rumorsが、「OM DigitalはOM‑10シリーズの開発を継続しないと明言した。今後生産が続くのはOM‑1/OM‑5/OM‑3シリーズだけになる」という“ワイルドな噂”を、アジアの情報筋からの話として掲載しました。
ポイントだけまとめると、
- 「OM‑10」を名乗るデジタル機は、少なくとも2025年内に出てくる気配はない
- そもそもシリーズ自体がいったん棚上げ(もしくは終了)されている可能性がそれなりにある状況
- ただし情報源はリークサイトのみの段階であり、公式の正式情報ではないので、26年以降の可能性は残されてはいる
という状態です。
OM‑10の噂タイムライン:期待から「開発中止説」まで
年 / 時期 | 出来事 | その意味(編集部の解釈) |
|---|---|---|
2023年末 | 「2024年初頭にOM-10登場か?」という初期リーク。E-M10 Mark IVベースの小改良版という見方が広がる。 | 期待値が一気に上昇。E-M10路線の正常進化が来るのでは?とコミュニティが盛り上がる。 |
2024年初頭 | OM-1 Mark II発表。8.5段IBIS、バッファ強化など上位機が大幅進化。 | ハイエンドが強化され、ラインアップ全体の“更新フェーズ突入”が明確に。次は中位〜エントリーが順番だと予想される空気に。 |
2025年2月 | OM-3発表。積層センサー+10bit 4K60p、クラシカル外観で話題化。 | ハイエンドとミドルの穴が埋まり、「次はエントリー=OM-10では?」という期待が再燃。 |
2025年6月 | OM-5 Mark II発表。418g、防塵防滴IP53、ライブNDなど“旅カメラ最適化”。 | エントリー帯をOM-5 Mark IIが兼任し始め、「OM-10の席が縮小している?」という声が増える転換点。 |
2025年8月13日 | 「OM-10シリーズの開発は継続しない」という未確認情報を43Rumorsが掲載。 | 初めて“開発中止”のワードが出て、OM-10の実現性が揺らぐ。 |
2025年8月14日 | 日本のニュースサイトも「E-M10シリーズ終了か?」と紹介。 | 国内ユーザーにも一気に広がり、コミュニティが騒然とする。 |
同時期 | インタビューでOM SYSTEM幹部が「E-M10 Mark IVは依然人気。方向性は今後も継続したい」と発言。 | “E-M10的なラインを完全に捨てるわけではない”という逆のニュアンスも存在し、情報が錯綜。 |
OM-10という型番は一度止まっている可能性が高いですが、一方で“E-M10的なエントリー機コンセプト”自体は存続の可能性はあります。2023〜2024年の期待値は高かったのですが、2025年に入り流れが反転しました。25年6月発売のOM-5 Mark IIが「エントリー兼ミドル」を埋めに来たことで、OM-10のポジションが薄くなっていることはうかがえます。
編集部としての見解:出るの?出ないの?
現時点の見解としては、
・「OM‑10」という名前での登場は、かなり望み薄
・ただし、E‑M10やPENの系譜を引き継ぐ“低価格・小型でカジュアルな新機種”が、数年以内に何らかの形で出てくる可能性はある
くらいに構えておくのが、現実的です。
「発売日予想」をあえて書くなら、
・“もし出るなら2026〜27年以降、そのときのラインアップや社内リソース次第”
・“そもそも別の名前(PEN系の新機種など)で出てくる可能性も高い”
と考えておくのが安全でしょう。
OM‑10とは何者か?噂の経緯を整理
2023年春、43Rumorsが「年内にOM‑10が登場するかもしれない」と報じた瞬間から物語は動き出しました。以来、国内外のサイトが断続的にリークを追補し、2024年末には“USB‑C必須のEU規制対策モデル”という観測も浮上。OM SYSTEM幹部は取材で「E‑M10ラインは継続する」と断言しており、水面下で開発が進むのは確実視されています。
初出リークが投下された背景
オリンパス時代からE‑M10シリーズは“手頃なプレミアム機”として人気を博してきました。買い替え需要が熟してきた2023年、サプライチェーンの動向を追う部品アナリストが小型マグネシウムボディと新型基板の発注を掴み、噂が拡散。真偽はさておき、ミラーレス市場のフルサイズ偏重に風穴を開けるニュースとして注目されたのです。
その後、MirrorlessRumorsが「2024年初頭発表」という追加情報を掲載。直近で実機が現れなかったことで“ガセ”扱いされる時期もありましたが、開発者インタビューの「E‑M10の精神は終わっていない」という一言が火を点け、期待は再燃。現在も信頼度70%前後で語られるホットトピックとなっています。
リークソースの信頼度を見極める
- FCC認証:無線モジュール登録を張っておくと“型番だけ先出し”を捕捉できる。
- 台湾経済紙:基板発注量の増減=量産スケジュールの体温計。
- 開発者登壇資料:製品名をぼかしたスライドに、次モデルの思想がにじむ。
噂の出所を鵜呑みにすると判断を誤ります。筆者が定点観測しているのはFCC認証の動き、台湾経済紙の部品出荷報道、そして開発者が登壇するカンファレンス資料です。名称が伏せられた新型マイクロフォーサーズ機が照合されるたびに「次こそOM‑10?」とネットがざわつく構図。複数情報が交差するときこそ客観視が必要だと肝に銘じましょう。
発売日はいつ?発表サイクルから読み解く
公式発表は無いものの、過去のOM SYSTEM製品サイクルを見ると“ハイエンド→ミドル→エントリー”の順で年一回ペースが定番です。2024年にOM‑1 Mark II、2025年春にOM‑3、同夏にOM‑5 Mark IIがリリース済み。となれば残る枠はエントリー機しかありません。CP+2026への合わせ技、あるいは年末商戦を狙う2025年11月発表説が濃厚です。
- 最有力:2025年11月発表→12月出荷
‑ Black Friday直後に開封動画が量産される、理想的なバズタイミング。 - 対抗馬:2026年2月CP+でお披露目
‑ 東京の熱狂を世界配信し、3月末決算に間に合わせるシナリオ。
EU USB‑C規制が後押し
2024年12月28日に適用開始されたEUの充電端子統一法では、Micro USBポートを持つ現行E‑M10 Mark IVが店頭から姿を消す恐れがあります。販路を守るためにもUSB‑C搭載の新型を早急に投入する必要があり、OM‑10を小改良モデルとして先行させる算段は十分あり得ます。
同社はOM‑1 Mark IIで既にUSB‑C採用済み。設計資産を転用すれば生産ラインの再構築コストも抑えられるため、2025年内ローンチは現実的です。部材調達の遅延が無ければ、Black Friday直前の発表で予約開始、翌月中旬出荷という流れが理想でしょう。
部品サプライチェーンのシグナル
台湾PCBメーカーの決算報告には「新規マイクロフォーサーズ基板量産でQ4増収見込み」との記載がありました。昨年のOM‑3も似たタイミングで照合されており、この“9月量産→11月発表”パターンは無視できません。輸送に1か月、国内リテール配備に数週間と考えると、2026年初頭でもおかしくはないのですが、ホリデー需要を逃すリスクを取るかどうかが最大の読みどころです。
予想価格と立ち位置:OM SYSTEM内での戦略
E‑M10 Mark IVはボディ8万円台で市場投入されましたが、昨今の円安とインフレを加味するとOM‑10は1割ほど高め、ボディ9〜11万円程度が妥当と見られます。キットレンズ付きで12万円、ダブルズームで14万円付近ならOM‑5 Mark IIとの価格階段が明確になり、併売戦略にも無理がありません。
- なぜ抑えられる?
- 防塵防滴を割り切りオミット
- CFexpressや2スロットを上位機に譲渡
- 既存USB‑C基板を流用し開発コスト圧縮
- それでも削らない!
- 5軸IBIS:夜スナ・動画に必須
- 視度付きEVF:晴天下でもフレーミングがブレない
- Bluetooth LE:スマホ連携の即効性
廉価でも削れない機能とは
入門機とはいえ5軸IBISと視度調整付きEVFは必須。これを省くとZV‑E10やEOS R100と同列に埋もれてしまいます。逆に防塵防滴やCFexpressスロットは上位機との差別化要素として敢えて省き、コストを吸収するプランが現実的。購入後に上位機へステップアップしたくなる“梯子”を用意するのがメーカーの巧妙な設計です。
さらに、USB‑C給電とBluetooth LE転送の採用はスマホ世代への決定打。撮影からSNS投稿までの待ち時間を最短化し、「スマホより楽しい」を体験価値として訴求できます。価格以上の快適さを感じさせる仕掛けが勝負の鍵でしょう。
レンズキットの巧みな誘導
噂の新キットズーム「10‑40 mm F4‑5.6」は換算20‑80 mm相当で旅・テーブルフォトをほぼ網羅します。単焦点沼に誘う導線としてはM.Zuiko 25 mm F1.8の同時購入キャンペーンが定番。ボディ+2本で15万円を切れば心理的ハードルは一段下がり、「最初の一眼にしては高いけど楽しいからOK」と背中を押されるユーザーは少なくないはずです。
スペック徹底推測:センサー・エンジン編
20 MP Live MOSセンサーは像面位相差AF対応版へ刷新される見込みです。TruePic Xベースの新エンジンを併用すれば、読み出し速度は前モデル比1.5倍に向上し、電子シャッター連写20コマ/秒も射程圏内。高感度耐性もISO12800常用レベルに底上げされると期待されています。※以下は複数リークの共通項を基にした予測仕様
項目 | 予想仕様 | 体感メリット |
|---|---|---|
センサー | 20 MP PDAF対応 Live MOS | 動体もビシッと追従 |
画像エンジン | TruePic X | ISO12800常用、連写20fps |
手ぶれ補正 | 5軸IBIS 5段以上 | シャッター1/8秒手持ちOK |
動画 | 4K30p無制限 / ALL‑I 200 Mbps | 長回しVlogでも熱停止知らず |
端子 | USB‑C 3.2 Gen1 / マイクIN | 配信・外部収録に即対応 |
AIノイズリダクションでJPEG仕上がりが激変?深夜スナップも“インスタ即アップ”レベルで完成するとの噂に期待が膨らみます。
積層型や裏面照射は乗るのか
積層・裏面照射センサーはコストが跳ね上がるため、エントリー機に搭載される確率は低め。ただしソニー製センサーの価格が近年下がり始めたことで、部分的に裏面照射構造を採り入れた“ハイブリッド版”が採用される可能性は残ります。もし現実となれば、ローリングシャッター歪みの低減やDR拡張が大きなアピールポイントになるでしょう。
一方、読み出しチャンネル数が増えるだけでも連写・動画性能は飛躍的に改善します。ハイフレームレート動画を強調してきたG9 IIやX‑S20に対抗するには、撮像系の刷新が不可欠です。
AIノイズリダクションの新潮流
TruePic X世代ではディープラーニングによる階調復元が進化し、シャドー部に乗る色ムラをマスクせず保持できると噂されます。Lightroomでのノイズ除去を前提にするより、カメラ内JPEGの完成度を高める方向性は“撮って出し文化”を支持するOM SYSTEMらしい選択。初心者ほどRAW現像に手を出しにくいため、アウト‑オブ‑カメラで作品になる画が得られるのは大きな武器です。
AF・手ぶれ補正・動画機能の進化点
像面位相差121点AFに被写体認識アルゴリズムを重ねれば、人物・鳥・鉄道・車の4系統を自動判別できると見られます。5軸IBISは補正効果5段以上を狙いつつ、電子手ぶれ補正併用で動画時の安定感も向上。4K30p無制限記録が叶えば、Vlogger層にも強烈なインパクトを与えるでしょう。
連写性能とバッファの課題
電子連写20コマ/秒は夢のようですが、実際にはバッファフルまで2秒弱という制限が付く可能性があります。そこでメーカーはライブNDやプロキャプチャー機能を推し、短い連写でも決定的瞬間を押さえられる体験を提案してくるでしょう。決定力を補完するファームウェアなら、ハード制約の印象を和らげることができます。
動画ではALL‑I 200 MbpsのH.265コーデックが噂されています。10bit内部記録はさすがに難しいものの、HDMI外部出力で4:2:2 10bitを得られればクリエイターにも刺さります。マイク端子の有無が最終判断材料になるユーザーは多く、搭載可否には注目したいところです。
ライブ配信時代の接続性
USB‑C 3.2 Gen 1を採用すれば、UVC/UAC対応でWebカメラ化がワンタッチ。配信用マイクをXLR‑Miniアダプター経由で接続できれば、エントリー機ながらラジオ収録やオンラインレッスンにも転用できます。スマホテザリング経由のリモート撮影が高速化すれば、現場からの速報投稿も格段にスムーズになるでしょう。
デザイン・操作性:小型ボディに宿る楽しさ
OM‑10の外観は“デジタルとフィルムの良いとこ取り”がテーマと囁かれます。E‑M10 Mark IV譲りのレトロフェイスをベースに、ペンタ部をわずかに高くし視度調整ダイヤルを大型化。前後ダイヤルにはアルマイト処理が施され、グリップは交換式で好みの厚みにカスタマイズできる可能性があります。
- 外観:E‑M10 Mark IV譲りの金属ダイヤル+革調グリップ。
- 液晶:下開きチルトとバリアングルを兼ねる“ハイブリッド式”構造。
- UI:スマホ感覚のフリックメニューで、設定迷子とはサヨナラ。
- カスタムグリップ:厚みを着せ替え、手の大きさも個性もフィット。
バリアングルか下開きチルトか
自撮り需要を考えればバリアングル優勢ですが、従来ファンは下開きチルトの素早さを支持。リーク設計図にはヒンジが中央寄りに描かれ、180度下方向へも回転可能な“ハイブリッド式”の可能性が浮上しています。これなら動画撮影時の横持ちと縦持ちのどちらでも利便性を確保できるでしょう。
グリップ交換式なら手の大きさに合わせた握りやすさを実現しつつ、携帯時は薄型にする二刀流が可能。小型ファスナーで固定する方式なら工具要らずで差し替えられ、アクセサリーメーカーが参入してカラフルなバリエーションが花開く未来も期待できます。
ダイヤルレイアウトとUI刷新
モードダイヤルは従来のP/A/S/Mに加え、「動画専用」「ライブND」「プロキャプ」アイコンが並ぶとリークされています。タッチUIはスマホライクなフリック操作に刷新され、撮影設定を階層化せずワンフレーズで呼び出せる“クイックメニュー”が実装される可能性も。新旧ユーザーの感覚差を埋めるUI進化は、カメラ離れを食い止める切り札になりそうです。
競合機比較:GX9・ZV‑E10・X‑T30 IIとの勝負
同価格帯を攻める三強と比較すると、OM‑10は“EVF+IBIS+コンパクト”という三拍子でキャラが立ちます。GX9はコントラストAF、ZV‑E10はファインダー無し、X‑T30 IIはIBISが無い──互いの弱点を平均点で塗りつぶす万能型がOM‑10の強み。画質でAPS‑C組に一歩譲っても、“撮りやすさ”と“持ち歩きやすさ”で逆転できる余地が大きいのです。
OM‑10 (予想) | Lumix GX9 | Sony ZV‑E10 | Fujifilm X‑T30 II | |
|---|---|---|---|---|
センサー | μ4/3 PDAF | μ4/3 CDAF | APS‑C PDAF | APS‑C PDAF |
IBIS | 〇 | 〇 | × | × |
EVF | 〇 | 〇 (Tilting) | × | 〇 |
動画4K制限 | 無制限予想 | クロップあり | 無制限 | クロップなし |
重量 | ≈380 g | 407 g | 343 g | 383 g |
💡 結論:全部入りでこの軽さ。街歩きカメラとして“反則級”。
GX9との兄弟対決
同じマイクロフォーサーズ陣営ながら、GX9は2018年発売とやや旧式。コントラストAFゆえ動体撮影に弱く、4K30p撮影ではクロップが発生します。PDAF搭載のOM‑10なら動体歩留まりが段違い。手ぶれ補正も最大4.5段→5段以上へ強化される見込みで、シャッター速度を稼げない夜景スナップでも有利です。
一方でGX9は防塵防滴に非対応。前モデルGX8は対応していたが、GX9では軽量化と引き換えに省かれた。とはいえ、Tilting EVFという独自機構が魅力。アウトドア用途では依然強敵になります。価格差が小さい場合、キットレンズの好みが最終決定打になるかもしれません。
ZV‑E10・X‑T30 IIとの棲み分け
ZV‑E10はAPS‑C×Vlog特化がウリで、内蔵マイクとバリアングル液晶が強み。ただしEVFレスで静止画を本気で撮るには少し心もとないのが実情。OM‑10はEVF装備で写真表現を重視するVloggerをガッチリ掴めます。2倍換算の望遠効果も野鳥・鉄道ファンには魅力。
X‑T30 IIはフィルムシミュレーションが唯一無二ですが、IBIS無しで手ブレに弱い点は譲れない弱点。OM‑10ならシャッター速度1/10秒でも歩留まりを確保でき、夜スナップ派の安心感が違います。APS‑C並みのボケ感を追求する層を除けば、トータルバランスでOM‑10優位といえるでしょう。
ユーザー像は誰?初心者からハイアマチュアまで
スマホ世代のエントリーユーザーに加え、フルサイズとの二台持ちを狙うハイアマ層がターゲットです。動画+スチル両立のVlogger、家族写真を高画質で残したい子育て世帯、小型システムで野鳥を追いかけるシニア──多様なライフスタイルの中核に「軽快さと確かな描写」を提供するポジションがOM‑10の真骨頂となります。
- スマホ卒業生:フィルター感覚で“作品”が量産できる。
- 旅行スナッパー:レンズ3本いれてもペットボトル1本分の重量。
- Vlogger:IBIS+無制限4Kでジンバル要らず。
- サブ機派ハイアマ:換算600 mmシステムをリュックに放り込める幸福。
初心者が感じる“楽しい”を拡張
撮ったその場でシェアできるWorkflowと、アートフィルターで作品化する手軽さは初心者のモチベーションを強烈に底上げします。OM‑10が備えるであろうスローモション動画や星空撮影アシストは「スマホには無い体験」を分かりやすく提供する仕掛け。初期設定のままでも驚きが得られ、学習曲線の傾きを緩やかにできます。
同時に、初心者が望遠やマクロに挑戦したくなったとき、レンズが小さく安価なマイクロフォーサーズ規格は大きな味方になります。10万円台で300 mm単焦点を揃えられる世界はフルサイズではまず不可能。成長に合わせてシステム拡張できる土壌が、新規ユーザーの離脱を防いでくれるでしょう。
サブ機需要を満たす仕様バランス
ハイアマチュアはメイン機で高画素フルサイズを使いつつ、サブ機に小型軽量なOM‑10を選ぶことで撮影領域を拡大できます。長距離遠征や山岳撮影では機材重量が死活問題。防滴仕様が無くとも、換算600 mm超のシステムがリュックに余裕で収まるメリットは代えがたい魅力です。
予約・購入ガイド:入手競争を勝ち抜くコツ
過去を振り返ると、エントリー機でも初回ロットは瞬間蒸発する傾向があります。確実に手に入れるには“公式オンライン+量販店ネット+実店舗”の三段構えが鉄則。発表日の午前中に各サイトのカートシステムへログインし、決済情報を事前登録しておくと決済失敗のリスクが減ります。
- 公式ストア・量販店・実店頭の“三刀流”予約
- 公開前夜に決済情報/ポイントカードをプリロード
- 在庫アラート+SNS通知で深夜キャンセルを拾う
- 旧機を下取り予約し、実質価格を底削り
- UHS‑II SDと予備バッテリーを同時確保して“開封即実戦”
在庫アラートとポイント二重取り
主要量販店は予約上限に達すると購入ボタンが灰色になりがちですが、深夜〜早朝にキャンセル分が復活するケースは珍しくありません。価格比較サイトの在庫アラートと公式Xアカウントの通知を併用すれば、チャンスを逃さず済みます。ポイント還元率を優先するか発売日入手を優先するかは悩みどころですが、記念モデルでない限り数週間待てば潤沢に流通する傾向も押さえておきましょう。
また、下取りキャンペーンを活用すれば実質負担を圧縮できます。E‑M10 Mark II以降の下取り価格は安定しており、キットレンズを含めると2万〜3万円の戻りも期待可能。新型到着と同時に旧機を手放すタイミングを計算しておくと損をしにくくなります。
アクセサリー同時購入のすすめ
予備バッテリーと高速SDカードは発売週に品薄になりやすい定番アイテム。特にOM‑10がUHS‑II対応なら、V60クラスのカードを一本押さえておくと動画撮影も安心です。保護フィルムや専用ケースは互換品が出揃うまで時間がかかるため、初期ロットを確保したい場合は純正オプションを同時購入しておくのが得策。
まとめ
噂の段階とはいえ、OM SYSTEM OM‑10が実体を帯びつつあるのは間違いありません。USB‑C搭載20 MPセンサーとPDAF、5軸IBISをコンパクトボディに押し込み、想定10万円前後という価格が実現すれば、入門機の常識を更新する一台になるでしょう。発売日直後の争奪戦を制するために、在庫アラートや下取りキャンペーンをいまのうちにチェックし、準備万端で発表を待ち受けましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。
あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨
みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!







.jpg?fm=webp&q=75&w=640)