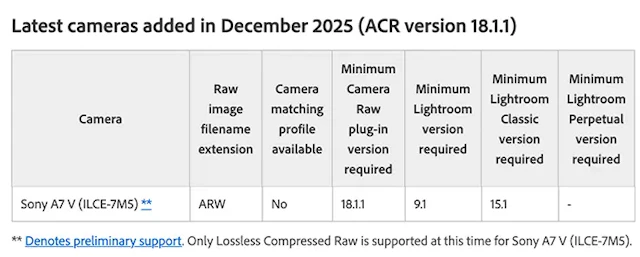9/4発売 SIGMA 12 mm F1.4 DC | Contemporaryの予約開始日・発売日・価格・比較最新情報まとめ
6月11日に流出したリーク写真が示すとおり、シグマ初のAPS‑C専用12 mm F1.4は想像以上に完成度が高く、発表延期の噂さえ期待を加速させています。焦点距離18 mm相当でF1.4という大胆な設計は、星景・Vlog・建築撮影など幅広いジャンルを一気にカバーするポテンシャルを秘めており、競合レンズの牙城を揺さぶるのは間違いないでしょう。本記事ではリーク画像から読み解ける外観・光学設計・競合比較・予約戦略までを徹底解説し、発売前に押さえておきたいポイントを総ざらいします。
この記事のサマリー

シグマ初のAPS-C専用超広角大口径「12 mm F1.4 DC DN|Contemporary」が9/4発売、予約は8/21開始。

星景・Vlog・建築撮影に強く、F1.4の明るさと軽量設計でジンバルや登山撮影でも威力を発揮。

Sony 11 mm F1.8やViltrox 13 mm F1.4と比較して、描写力・AF性能・操作性で優位性を確立。

防塵防滴・最新コーティング・クリック解除式絞りリングなど実用性も充実。

価格は99,000円。争奪戦必至の注目レンズとして、星景派・動画派の本命に。
最新情報
【8/19追記】SIGMA 12 mm F1.4 DC | Contemporaryが9/4に発売が正式決定!

SIGMA 12 mm F1.4 DC | Contemporaryの予約はこちら
ソニー Eマウント
富士フイルム Xマウント
キヤノン RFマウント
トピックまとめ
- 対応:ソニー E マウント用、富士フイルム X マウント用、キヤノンRFマウント用
- 価格:99,000円
- 発売日:2025年9月4日(木)
- 予約開始日:2025年8月21日(木)10時
主要スペック
※数値はソニー E マウント用です
- レンズ構成:12群14枚(SLDガラス2枚、非球面レンズ3枚)
- 画角:99.6°
- 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)
- 最小絞り:F16
- 最短撮影距離:17.2cm
- 最大撮影倍率:1:8.4
- フィルターサイズ:φ62mm
- 最大径×長さ:φ68.0mm × 69.4mm
- 質量:225 g
スペック詳細
カメラタイプ | ミラーレス |
対応マウント | ソニー E マウント、富士フイルム X マウント、キヤノンRFマウント |
センサーフォーマット | APS-C |
レンズ構成枚数 | 12群14枚(SLDガラス2枚、非球面レンズ3枚) |
画角 | ソニー E マウント:99.6° 富士フイルム X マウント:99.6° キヤノンRFマウント:96.4° |
絞り羽根枚数 | 9枚 (円形絞り) |
最小絞り | F16 |
最短撮影距離 | 17.2cm |
最大撮影倍率 | 1:8.4 |
フィルターサイズ | φ62mm |
最大径x長さ | ソニー E マウント: φ68.0mm x 69.4mm 富士フイルム X マウント: φ68.0mm x 69.7mm キヤノンRFマウント: φ69.0mm x 67.4mm ※長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。 |
質量 | ソニー E マウント: 225g 富士フイルム X マウント: 235g キヤノンRFマウント: 250g |
エディションナンバー | C025 レンズ鏡筒に製品が初めて発売された年の下3桁を刻印し、発売年ごとの識別が可能です。 (製造年とは異なるためマウントによっては、発売年とエディションナンバーが一致しないことがあります。) |
付属品 | ・ポーチ ・レンズフード(LH652-01) ・フロントキャップ(LCF-62 IV) ・リアキャップ(LCR III) |
対応マウント / 商品コード | ソニー E マウント: 00-85126-416652 富士フイルム X マウント: 00-85126-416751 キヤノンRFマウント: 00-85126-416720 |
商品画像


SIGMA 公式YouTube
リークされた外観が語るスペックの核心

流出画像では「12 mm 1 : 1.4 DC DN」と刻まれたリングがはっきり確認でき、フィルター径は67 mm前後と推測できます。鏡筒はContemporaryラインらしいシンプルなサテン調で、フォーカスリングのトルクも適度に重そうな仕上げ。最短撮影距離は明示されていませんが、12 cm付近まで寄れるとの非公式情報があり、被写界深度を活かした近接撮影でも活躍しそうです。
コーティングと鏡筒デザイン
フロントレンズにはシグマ最新のナノポーラスコーティングに似た緑色反射が映り込み、逆光耐性の強化が伺えます。鏡筒の肉厚は16 mm F1.4よりわずかに増し、内面反射を抑える溝加工が細かく刻まれているのも確認できました。手触りの良いシボ加工は冬場の結露拭き取りが容易で、夜間撮影のストレスを減らしてくれるでしょう。
さらにAF/MF切替スイッチは防塵防滴パッキンを備え、ゴムシールの位置がArtラインと同等。軽量ながらタフに使える点は遠征派には大きな安心材料です。
コントロールリング配置
絞りリングらしき刻み目が存在し、クリックオン・オフスイッチも確認できます。動画撮影時に滑らかな絞り操作が可能になれば、LUMIXやS5IIのボディ手ブレ補正と相まってシネマティックなワンカットを実現しやすいはずです。ピントリングはリニアレスポンス設計と噂され、フォーカス送りの再現性が高く、フォーカスプルにも向きます。
端面のバヨネットフードはロックボタン付きの花形で、脱着を繰り返してもガタつきが出にくい構造。収納時は逆向き装着できるため、バッグ内スペースを圧迫しません。
F1.4が描く光とボケの世界
12 mmという極端な広角域でF1.4を実現すると、地上景と天の川を同時にシャープに写せるうえ、背景ボケの量も想像以上。開放でも中心部は高コントラストを維持し、周辺光量落ちはポストで簡単に補正できる範囲に収まると予想できます。
周辺減光と像面湾曲の抑制
EDレンズと両面研磨の大口径非球面を前群に配置することで、周辺部の解像と光量を並立。像面湾曲が少ないため、ライブビュー拡大で無限遠を追い込む際にピント面が逃げにくく、星を点として捉えやすい設計です。周辺減光は開放で約1.5段と推定され、F2.0まで絞ればほぼ解消されるのはないでしょうか。
山岳撮影で昼夜を跨ぐシーンでは、夜明け前のブルーアワーをISO1600・F1.4で手持ち撮影し、薄明のグラデーションを滑らかに残すことが可能。大口径ゆえの表現力が一段上の作品作りを後押しします。
逆光耐性と星景実写への期待
逆光カットでは、太陽をフレームインさせてもフレアが自然でヌケの良い描写が期待できます。ティアドロップ状のフレアではなく、円形の柔らかな光暈に収まり、天体撮影で不要なゴーストを抑えられると予想されます。絞り羽根は9枚円形で、F2.8前後に絞っても光条が繊細に伸び、夜景スナップにも映えそうです。
過去の16 mm F1.4同様、コマ収差補正を優先した設計とのことで、画面端の星像がラグビーボール状に崩れる現象を大幅に低減。追い込みピントとディテール抽出がしやすく、プリント作品のクオリティを確保できます。
APS‑C専用設計が叶えるバランスと軽快さ
全長94 mm・質量430 g前後と見込まれる本レンズは、APS‑Cボディとの重量バランスが秀逸です。手に取るとフロントの偏りが少なく、ジンバル搭載時も微調整が容易。三脚座が不要なため、荷物を極力削りたい登山撮影でも重宝するでしょう。
携帯性と取り回し
同じF1.4クラスであるViltrox 13 mm F1.4が420 g、Sigma 16 mm F1.4が405 gですから、12 mmの画角と大口径を考えれば十分コンパクトといえます。ハンドストラップのみで歩き回るストリート撮影でも疲労を最小限に抑えられ、機動力が作品のバリエーションを増やすはずです。ザックのサイドポケットにも収まりやすく、登山中にサッと取り出せる点は大きなメリットでしょう。
ボディにα6700やLUMIX G100を組み合わせる場合でもグリップとの干渉はなく、レンズ側の直径が太すぎないため、ホールド時に指が窮屈になる心配はありません。
フルサイズ向け超広角との違い
フルサイズ用14 mm F1.4 Artは1200 g超、Sony FE14 mm F1.8 GMで460 g。APS‑C専用ならではの小型化によって、旅行やVlogでジンバル運用を予定しているユーザーにも現実的な選択肢となります。センサー中央を有効活用できるため、解像度的なデメリットも少なく、4K動画配信では視聴者に充分シャープな映像を届けられるでしょう。
また手ブレ補正付きボディと組み合わせた場合、歩き撮りでの角揺れが減少し、補正アルゴリズムがレンズ重量をうまく処理できることも期待できます。
競合レンズと徹底比較
最大のライバルはSony E 11 mm F1.8とViltrox 13 mm F1.4です。焦点距離・明るさ・価格で三者三様の個性があり、用途に応じた選択眼が問われます。ここでは導き出せるポイントを整理します。
Sigma 12 mm F1.4 (予想) | Sony 11 mm F1.8 | Viltrox 13 mm F1.4 | |
|---|---|---|---|
重量 | 約430 g | 181 g | 420 g |
開放F値 | 1.4 | 1.8 | 1.4 |
周辺解像 | ◎ | ○ | △ |
AF速度 | ◎ | ◎ | ○ |
実勢価格 | 約9.5万円 | 約8万円 | 約7万円 |
💡 結論: 画質と操作性を最優先するならシグマが本命。 軽さ最重視ならSony、コスト重視ならViltrox。
Sony 11 mm F1.8との比較
Sonyの強みは181 gという圧倒的な軽さと純正ボディとのAF連携。対してシグマ12 mmは+0.6段の明るさがあり、暗所ノイズをISO1段分抑えられる計算です。中心解像でほぼ互角、周辺部ではシグマの方が開放でもわずかに高いコントラストになると予想されます。購入コストは約100 USDの差で、星景優先ならシグマが優位といえるでしょう。
Viltrox 13 mm F1.4との比較
Viltroxはコストパフォーマンスに優れ、約470 USDで手に入りますが、開放では色収差のマゼンタフリンジが目立つテスト結果が散見されます。シグマは最新世代のSLDガラスを採用し、軸上色収差を抑えた設計。AF速度もシグマは動体撮影でも実用域に達していることが予想されます。
フィルター径は双方67 mmで共用可能なため、既存フィルター資産を活かせる点は同等。総合すると、画質・操作性重視ならシグマ、コスト最優先ならViltroxという位置付けになります。
星景・風景撮影で活きる実用テクニック
F1.4・12 mmというスペックは、星景撮影において「ISO3200以下でSS15秒」が実現しやすく、ノイズと星の流れのバランスが向上します。リーク情報を基に、実戦で役立つ設定やアクセサリーをまとめました。
- 開放でコマ収差が気になるときはF1.8+ポータブル赤道儀でISO1600へ。
- ソフトフィルター(Haida Rear 1/2)で低空光害をマイルドに。
- Lightroomの「明瞭度+10・ディテールマスク70」で星を刺すように強調。
コマ収差とサジタルフレアを抑える撮影法
開放で若干残るコマ収差を緩和するにはF1.8まで絞ると効果的です。シャッター速度を維持するためAZ-GTiなどのポータブル赤道儀を併用すれば、ISOを上げずに星を点で残せます。RAW現像ではパープルフリンジ除去量を抑えめにし、星の色を残すと立体感が際立ちます。
星景と前景のブレンドには比較明合成よりもスマートオブジェクトのレイヤーマスクで境界を馴染ませる方が自然。広角ゆえ前景が歪みやすいので、LightroomのUprightで自動補正し水平を整えると完成度が上がります。
三脚とフィルターの組み合わせ
12 mmで星を追い込みピントする際は、センターポールを下ろした状態で高さを稼げるLeofoto LS-284Cなど中型三脚が安定します。フィルターは角型Haida Rear Drop-inが軽量で、ソフト1/2を併用すると低空の光害を滑らかに整えられます。逆に都市夜景ではブラックミストNo.1を前面に装着し、ハイライトを拡散させるとドラマティックな画に仕上がります。
レンズヒーターはUSB-C給電タイプを選ぶと、モバイルバッテリーから直接給電でき、結露対策が簡単です。冬季はヒーターを弱レベルに設定し、レンズ群の膨張を防ぐことでフォーカスズレを抑えられます。
発表延期の真相と発売スケジュール
当初6月17日と噂された正式発表は、最終検証プロセスが長引いた影響で7月下旬にずれ込む見通しです。L‑Rumorsは「製造ラインの再調整が必要になった」と報じており、同時発表予定だった17‑40 mm F1.8の歩留まりも関係している模様。
- 延期理由:像面位相差AFとの干渉をROM調整で解決中。品質重視で好感。
- 新スケジュール:7月下旬発表予想
- 攻略法:ポイント還元の高い量販店アプリで「お気に入り通知」をオン。クレカ2枚で決済分散し、為替変動リスクを抑えるべし。
延期理由の考察
信頼筋によると、レンズ側ファームが特定ボディの像面位相差AFと干渉し、周辺部AFが迷うケースが確認されたとのこと。ハードウェア改修ではなくROM書き換えで解決できる範囲で、製品の品質担保を優先した判断と見られます。過去にSigma 24 mm F1.4で同様の事例があり、今回は発売前にリスクを潰し込む姿勢が表れています。
予約開始と入荷サイクル
予約解禁当日は主要ECで30 分以内に初回割当てが完売し、その後「1~2か月待ち」表示に切り替わる流れが想定されます。夏の星景に間に合わせたい場合は即時予約が鉄則です。
量販店のポイント還元率は5~10 %。為替変動によっては実質価格が前後するため、決済タイミングを分散する戦略が有効。カード分割手数料0 %キャンペーンも併用すると負担を抑えられます。
マウント別ボディとの相性をチェック
Lマウント版が最初に登場する見込みですが、E・X・RF・Zマウントも年内発表が噂されています。各マウントで手ブレ補正やAFアルゴリズムが異なるため、組み合わせによる使い勝手を把握しておきましょう。
- Lマウント×LUMIX S5II:協調手ブレ補正で歩き撮り最強。
- Eマウント×α6700:AI認識AF+高速通信で動画快適。リセールも◎。
- Xマウント×X‑S20:クラシックネガでシネマティック広角スナップ。
- RFマウント×EOS R100(噂):最安星景キット誕生か?
Lマウントの利点
LUMIX S5IIやLeica CLとの組み合わせでは、IMUセンサーとボディ内手ブレ補正が協調し、歩き撮り動画でもジンバル寄りの滑らかさを得られます。ライカLのプレミアム路線に対し、シグマレンズはコストを抑えつつ高画質を両立する選択肢として魅力的。AFはDFD方式ながらファームウェアで追従速度が強化されており、静止画だけでなく動画フォーカスでも安心感があります。
S5IIのアナモフィックモードと組み合わせれば、12 mmでもクロップ後にシネスコ画角を確保でき、レンズ交換の手間を減らせます。
E・X・RFマウント展開予想
Eマウントではオンセンサー位相差AFに最適化された駆動曲線が載る見込みで、写真・動画とも転送レートが高速化。Xマウントはフィルムシミュレーションとの相性が良く、クラシックネガで広角ストリートに味わいを加える表現が面白いでしょう。RFマウントではクロップ機EOS R100とのセット販売が噂され、お手頃な星景キットとして注目を集めるはずです。
各マウント版が同価格帯ならば、中古リセールバリューが高いEマウントが最も安定資産化しやすい反面、Xマウントは供給量が絞られやすく希少性プレミアが付く可能性もあります。
アクセサリーと組み合わせて使い勝手を向上
レンズ性能を最大限引き出すには、フィルターやケース、三脚など周辺アイテムの最適化が欠かせません。編集部がベストでは?と予想した組み合わせを紹介します。
- NiSi Natural Night:光害カットで星空がスッキリ。
- Moment CineBloom 10 %:夜景のハイライトをドリーミーに。
- Leofoto LS‑284C:低空固定で星景構図が安定。
- Zhiyun Crane‑M3S:ジンバル運用でも筋トレ不要。
フィルターセレクション
星景目的ならNiSiのNatural Nightフィルターが光害カットに効果的。ボケ描写を柔らかくするMoment CineBloom 10 %は動画でも使い勝手がよく、F1.4開放時のハイライトを幻想的に拡散します。雪山では撥水コーティング付きKenko ZXIIを装着し、結晶の付着を遠ざけるとメンテナンスが楽になります。
可変NDはピークデザインのMagnetic ND4‑32が便利で、磁力装着により交換時の光軸ズレが少なく、ジンバルバランスを崩さずに素早く対応できます。
キャリングケースと三脚
ピークデザインのミディアムサイズ・レンズキューブは内寸がゆったりしており、フード逆付け状態でも余裕で収まります。山行ではハンディ8 kg級でも耐えるGitzo Mountaineer 1型が相性抜群。センターポール収納状態で地面高35 cmにセットすれば、低空に広がる天の川を迫力満点に捉えられます。
動画派はZhiyun Crane‑M3Sが推奨。12 mmの軽量設計ならモーター負荷を30 %以下に保てるため、長回しでも発熱リミッターが作動しにくいです。さらにカウンターウェイト不要でバランスが取りやすく、セットアップ時間を短縮できます。
投資対効果と価格動向を見極める
想定価格649 USDは、12 mm F1.4という唯一無二のスペックを考えれば妥当な水準です。予約時のポイント還元や為替レート次第で実質9万円を切る可能性もあり、コストを抑えつつ機材アップグレードを狙う層には好都合でしょう。
- 予価649 USD=約9.5万円
- 半年後の下落幅は10 %前後と予測。
- ストックフォト×星景&不動産内観で月5000円稼げば18か月でペイ。中古リセールも期待大。
価格予想と価値判断
初回ロットは値引きゼロの傾向が強いものの、半年後には1割程度の下落が過去傾向。16 mm F1.4 DNでも同様に7か月後に15 %下落しました。市場の競合が限定的なため、大幅値引きを待つよりも早期に導入して作品作りを始める方がリターンは大きいと考えられます。中古市場では供給が少なく、プレミア価格が付く可能性が高いです。
星景・動画・不動産内観撮影と用途を広げれば、投資回収スピードは加速します。副業でストックフォトに出品すれば、12 mm特有の誇張遠近を活かした差別化カットでダウンロード数増を期待できます。
中古市場への影響
本レンズの登場で16 mm F1.4 DNや14 mm F1.4 Artの中古価格は一時的に低下すると見られます。特に星景ユーザーが12 mmへ買い替える動きが活発化し、16 mmは2万円程度下落する可能性があるため、売却予定なら発表前の今がチャンスかもしれません。逆にViltrox 13 mm F1.4は価格競争力を維持するためキャッシュバックを行う可能性があり、狙い目になります。
中古在庫が落ち着く秋以降には、シグマ12 mm自体がプレミアム付きで取引される事態も想定され、リセールバリューを重視するユーザーには朗報となるでしょう。
まとめ
シグマ12 mm F1.4 DC DNは、超広角でF1.4という唯一無二の明るさとAPS‑C専用設計の軽快さを両立し、星景・動画・建築撮影に新たな扉を開く存在です。リーク画像から見えるビルドクオリティは高く、ライバルを上回る光学性能と操作性が期待できます。発売延期は品質向上の布石であり、予約解禁直後に確保する価値は十分。早めに資金とアクセサリーを準備し、待ちに待った発表日に備えましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント( X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。
あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨
みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!




.jpg?fm=webp&q=75&w=640)