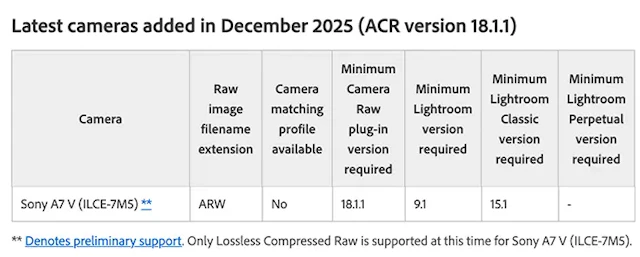.webp?fm=webp&q=75&w=1152)
【リーク】ソニーの視線入力AF特許公開。キヤノン実装との比較で見る
視線でAF枠を動かす「視線入力AF」をめぐり、ソニーがファインダー構造に関する特許を取得しました。公開情報から読み取れるのは、接眼部まわりに「検出光透過部」を設け、発光部(赤外)配置を最適化して小型化と検出安定性の両立をねらう設計思想です。この記事では特許公報に基づき要点を整理し、今後の見通しやキヤノンの類似実装との比較などを説明します。
この記事のサマリー

特許の核心:接眼部に「検出光透過部」を設け、視線検出の赤外照射経路を確保しつつ小型化を図る

発光部の対称配置や導光体の採用など、設計オプションが請求項で提示。一方で製品化は確定していない

運用面:視線で対象を確定→被写体検出・追尾に委ねる流れが実機(キヤノン)でも確認できる

競合のキヤノンはEOS R5 Mark II / EOS R1で視線入力AFを実装

キヤノンとの違いは「構造の着眼点」。ただしビームスプリッター使用可否は資料から一律に断定しない
要点ダイジェスト:ソニー視線入力AF特許の核心
.webp?w=320)
10/15に発行された特許公報(出願番号:P 2023506776)によれば、発明名称は「ファインダー及び撮像装置」。権利者はソニーグループ株式会社と記載されています。課題は「視線検出装置の組込みでファインダーが大型化しやすい」点にあり、接眼部の設計で小型化と検出の安定性を両立させるのが狙いです。
特許情報はあくまでも設計案であり、製品化が確定しているわけではないことを留意しましょう。
特許で示された課題意識
ファインダー内部に視線検出の部材を収めるとスペースが逼迫し大型化に直結します。さらに発光が角膜で反射され受光部に戻る過程の安定性も確保が必要です。本特許はこうした制約を踏まえ、接眼光学系の周辺に部材を過度に追加せず、赤外の入出射を確保する枠組みを与えています。
とくに、視界(可視像)を妨げない形で検出光(赤外)を角膜に送る位置関係が重視され、出射位置は「接眼光学系の最外周より内側」に置くなど、幾何配置の条件が請求項で定義されています。
解決アプローチの骨子
請求項1〜5は、接眼部の遮光体(ファインダーカバー等)の一部を赤外が通る「検出光透過部」として設け、そこから角膜へ検出光を導く構成を規定します。この結果、可視像の遮光を維持しつつ赤外の通り道を確保できます。なお、受光側光路(反射光の導出)についてビームスプリッターの使用可否は請求項からは限定できません。
また請求項8〜9では発光部の対向配置や複数配置、請求項10〜11では発光を導く「導光体」の採用も例示されており、組み合わせ次第で個体差や姿勢変化へのロバスト性向上が期待できます。
ハード構成の要:IR発光・受光と検出光透過部の最適化
読み解きのポイントは、赤外の入出射を最短経路に保ちながらファインダーの覗き心地を損なわないこと。検出光の出射位置を接眼光学系の内側に設定し、遮光体の一部に「検出光透過部」を設けることで、可視像の遮光と赤外の透過を両立させる設計です。
IR照射と発光配置の考え方
発光部を光軸の左右に対称配置(請求項8・9)すると、角膜反射のムラを抑えやすく、装用状態や姿勢の変化に対して検出の安定域を取りやすくなります。発光部を被写体側に置く構成(請求項7)や、導光体で出射面を形成する例(請求項10)も提示され、量産実装の裁量幅が確保されています。
これらの要素を接眼周辺にコンパクトに集約することで、筐体の小型化や配線・遮光処理の単純化につながる余地が示唆されます。検出精度の安定は、初期指定の確度を左右するため、構造設計の寄与は大きいでしょう。
検出光透過部を設ける利点
遮光体の一部に赤外のみを通す「検出光透過部」を設けると、可視像の覗きやすさ(遮光)を保ちながら、赤外の照射経路を確実化できます。これにより、アイポイントや見えの悪化を最小限に抑えつつ、赤外の入射角・出射位置を設計通りに確保しやすくなります。受光光路の具体方式(ビームスプリッターの有無など)は本特許の請求項では限定されていない点に留意が必要です。
EVFの高精細・高フレームレート表示と両立しやすい構造であれば、視野内の初期ポイント指定を遅延少なく行える素地になります。可視像と赤外の役割分担を構造的に整理する発想は、長時間の実務でも有効です。
視線×認識の基本フロー:直感選択と追尾の役割分担
実際の使用では「視線で主語を素早く確定→以降の追尾は被写体認識に委ねる」という役割分担が合理的です。実機の例として、キヤノンの公式マニュアルは視線で被写体を確定した後、サーボAFで追尾を継続する手順を案内しています。
初期取得は視線、粘りはAI
フレーム内に被写体が多数ある場面でも、視線で「誰を追うか」を即時に示せます。確定後の追尾はカメラ側の認識に任せることで、再捕捉や遮蔽に強くなります。
タッチやマルチセレクターのみで遠距離を移動させるより、視線ならフレーム端から端までのジャンプが素早く、入力負担を抑えられます。視線の役割を「主語指定」に寄せると安定します。
誤選択のリカバリー
誤って隣の被写体に確定した場合は、半押し解除→再半押しで再確定、あるいは一時的に視線入力をオフにしてジョイスティックで安全に退避する運用が有効です。
キャリブレーションの勘所:環境と装用状態で複数登録
視線入力AFの精度は初期キャリブレーションが左右します。キヤノンのマニュアルでは、横位置/縦位置を分けて複数回行い、同一番号に蓄積させる運用や、裸眼・眼鏡・コンタクト別の登録が推奨されています。
環境別・姿勢別の登録
周囲光や姿勢の違いで瞳孔の見え方は変化します。横/縦それぞれで数回繰り返すと精度が向上し、同じ番号に蓄積していくことが案内されています。屋外ではEVFへの太陽光入射を避ける等の注意点も明記されています。
機種により、キャリブレーションデータの保存・読込に差があります。EOS R3は最大6件登録およびカード保存/読込が可能と報じられています。R5 Mark II / R1は複数番号の運用が可能ですが、上限の明示は見当たりません。
眼鏡・コンタクト対策
近赤外線カットやミラー加工の眼鏡、ハード/カラーコンタクト等は検出を阻害する場合があります。装用状態ごとに登録番号を分ける運用が推奨されています。アイカップの使用推奨も公式資料に記載があります。安定しにくい場合は、登録済み番号の切換え→再キャリブレーションの順で対応すると再現性を取りやすくなります。
ソニー特許の読み比べ:競合方式との違いを押さえる
競合のキヤノンはEOS R5 Mark II / EOS R1で視線入力AFを実装。視線で被写体を確定し、サーボAFで追尾する運用が公式に案内されています。一方、ソニーの特許は接眼周りの構造(検出光透過部、発光部の配置、導光体等)を請求項で明確化しており、小型化と安定照射の両立に着目しているのが読み取れます。
光学的な設計ポイントの差
本特許は「遮光体の一部を検出光透過部として設ける」「発光部を光軸を挟んで配置」「導光体で出射面を形成」など、接眼部における赤外光の通し方を構造面から定義しています。キヤノン側はIR照射と専用センサーでの検出を前提に運用が説明されます。いずれもビームスプリッターの使用可否を一律に断定できる公開情報ではありません。
評価軸としては、初期指定の速さ、追尾の粘り、誤選択からの復帰容易性(操作体系)が実体験に直結します。方式差は、最終的にはユーザー体験にどう還元されるかで判断するのが合理的です。
対応ボディに求められる条件:EVFと処理系
視線入力の体感は、EVFの解像・応答とAF/認識の処理遅延のバランスで決まります。表示遅延が小さく、視線確定から追尾開始までの一連の応答が滑らかなほど歩留まりが上がります。
EVF側の要件
高精細・高リフレッシュのEVFは視線ポインターの追従性に有利です。輝度余裕やアイポイント、視度調整範囲も眼鏡ユーザーの再現性に影響します。
パン時の残像が強い表示モードでは狙いの保持が難しくなるため、応答性重視の表示プロファイルを選ぶのが無難です。
演算系・電力の配分
視線検出・被写体認識・手ブレ補正・動画処理など同時動作の優先順位設計が重要です。ファーム更新で追従性が改善される余地もあるため、更新情報は定期的に確認しましょう。
なお、ソニーの本特許はファインダー構造に関するもので、実装時の演算資源配分やUI仕様は別設計となる可能性があります。
キヤノン方式から学ぶ運用知見
キヤノンの視線入力AF(EOS R5 Mark II / EOS R1)は、キャリブレーションの複数登録、視線での確定とサーボAF追尾の併用、オン/オフのボタン割当など、実運用に直結するガイダンスが公式に整備されています。
校正と使い分けの作法
横/縦それぞれで複数回キャリブレーションし、同じ番号に蓄積する運用が案内されています。視線で素早く対象を確定し、追尾はカメラに任せる一連の動作がベースです。
視線の苦手な配置が続く場面では、潔くタッチ/ジョイスティックへ切り替え、歩留まりの安定を優先する判断が有効です。
「合わない日」への対処
眼のコンディションで精度は変動します。あらかじめ停用ボタンを身体化しておき、誤選択が続くときは使用頻度を下げる運用が推奨されます。視線入力は「主語指定の高速化」に使い、後段は追尾に委ねる割り切りが結果的に成功カットを増やします。
技術的注目点:特許の数値情報と読みどころ再確認
書誌事項:登録日2025-10-06、発行日2025-10-15、発明名称「ファインダー及び撮像装置」、出願番号P 2023506776、権利者はソニーグループ株式会社。先行技術の例示や請求項(全12項)も公開されています。
課題→目的→構造の三段構え
課題:ファインダーの大型化を抑えつつ視線検出を確保。目的:角膜への効率的な照射と受光のための経路設計。構造:遮光体の一部を検出光透過部とし、発光部の配置や導光体の採用で安定度を高める。
総じて、接眼部の見え(遮光)と赤外の通り道(透過)を両立する具体策が請求項で整理されています。
まとめ
ソニーの特許は、接眼部に「検出光透過部」を設けるなどの構造で、視線入力AFの実装における小型化と照射安定の両立を狙う内容です。ビームスプリッター使用可否の断定は避け、公開された請求項から読み取れる要素に基づいて評価するのが適切です。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
撮影テクから最新ギア情報まで、“次のステップ”を後押しするネタをみんなのカメラSNS公式アカウント(X / Threads / Instagram / TikTok / YouTube )で毎日発信中。
あなたの作品がタイムラインに流れる日を、編集部一同楽しみにしています📷✨
みんなのカメラのアプリでは、最新のリーク情報や人気商品の予約・在庫情報をプッシュ通知でお届け!無料ダウンロードはこちら!



.jpg?fm=webp&q=75&w=640)